
赤鹿麻耶。大阪に生まれ、現在も大阪を拠点に活動を続ける写真家。2011年、『風を食べる』で「第34回写真新世紀グランプリ」を受賞し、気鋭の写真家としてその名が知られるようになる。
以来、大阪・桃谷の空き地や東京・新宿区の銭湯を会場に大胆な展示方法で独自の空間をつくり上げた「Did you sleep well?」(2015年)や、夢をテーマにした「大きくて軽い、小さくて重い」(2017年)、アーティスト・イン・レジデンスとして台湾で制作された「Be my landscape」(2017年)、ドイツ・フランクフルトのカフェが展示会場となった「Sweet Rainy City」(2019年)など、国内外での個展の開催や、コロナ禍に東京都写真美術館で開催された「あしたのひかり 日本の新進作家 vol.17」(2020年)といったグループ展への参加など、多様なテーマ、展示形態で作品を発表し続けている。
インタビュー後編では、コロナ以降の日々の中で考えていること、日本や海外の風景の見え方の違い、価値観が大きく変わった瞬間についてといった話題を通して、赤鹿さんの今後の展開を予感させるお話を伺うことができた。

考え続けること、自分を“手放す”こと
――「HEP FIVE」のお仕事以外だと、コロナのことがあって変化などありますか?
赤鹿:コロナが無かったら今もたぶんあっち行ったりこっち行ったりしてたはず。今は止まってみて、写真を見返したりもしていますね。ここ5年ぐらい、なんかバタバタしていて、海外に行くことも多かった。海外に行くとつくった気持ちになっちゃうじゃないですか。ずっとたくさんつくっている気持ちだったんですけど、ほんまにそれが作品なのかどうかっていうのをもう1回見返す時間にもしていますね。
――さっきおっしゃっていた“作品かどうかの見極め”のような。
赤鹿:ずっと昔から、とにかくたくさん作品をつくろうと思っていて、それは数の呪いですよね(笑)。最近、それってちょっと間違ってるなと思いはじめていて。「いっぱいあるからいい」じゃないんやと。真っ白な壁とかもらって「ここで展示して」とか言われても、私って「余白が怖いさん」なんです(笑)。「サービスせな! いっぱい貼らな!」みたいな。なんでたくさん貼ろうとしたり、たくさんつくろうとしたりするんかなと自分でも考えたりするんですけど。学生時代って、毎回プリントしたものを学校に持ってきて、先生と一緒に1枚ずつちゃんとどれがどうなのか見ていましたね。海外とか行けなかったから、喫茶店で5時間とか6時間、「こんなんつくりたい!」ってノートにスケッチして。ここ数年は、撮ったらデータを置いて次の地へ、みたいな感じやったから。いま、コロナで外に出られへんってなったらまた頭が働き出して、デッサンっていうほどかっこいいもんじゃないですけど、また描いたり。海外に行けないから、中国の映画を見て思いを馳せて、それがインスピレーションになったり。
――海外ではなく、近所の生活圏から得るインスピレーションみたいなものもありますか?
赤鹿:そういう時期もありました。ホームセンターに行ったり、おばさんがゴミ出しする姿からインスピレーションを受けたり。でも、やっぱり日本って“デオドラントユートピア”(※)というか。匂いがない気がします。私、匂いのあるところがすごく好きなんですよ。高校の時に最初に行ったのが中国だったんですけど、中国には匂いがあって。日本ってほんま無臭やなってよく思っちゃうんですけど。
※巖谷國士著『シュルレアリスムとは何か』(ちくま学芸文庫)の言葉を引用している。赤鹿さんいわく「ものすごく勉強になった」とのこと
――なるほど。物足りなさというか。
赤鹿:道とか建物が一緒というか、日本は地震もあって耐震もしないとあかんから、整備されてしまっていて。台湾行ったら道がグネグネうねっていて、「あれがシュルレアリスムの世界の入り口か」と思って、夢のような感覚になる。かといって日本になんもないって決めつけたらあかんと思って、歩いたりもしています。「なんかオバケみたいやな、日本の感じ」って。歩いていて、まちの景色が半透明な感じ、私が消えかかってる感じがするんです。

赤鹿:今、“私がそこにいないような写真”をつくろうとしていて。これまでだと「ここに私がいます!」みたいになっちゃってたんですけど、私の力を最小限にして、誰がつくったんかようわからないかもしれない、半透明のようなものをつくろうと思って。ただ、そうするとあんまりパッとしない写真になってくるんですよ(笑)。「じゃあ、なんでそんなものをつくろうと思ってんのかな」ってよう考えたら、ひとつは自分の演出が自分で気持ち悪くなるっていういつものやつなんですけど、「今、日本の景色や人のなかからイメージをつくろうとしてるからやん」と思って。自然にそうなるんやなって。ファーッとしていて、あるようでなかったり、みんながたまに半透明に見えたり。消え入りそうな感じを今は写真作品としてつくろうとしてるし、日本がそういうふうに見えてますね、私には。
――つかもうとしてもつかめないような。
赤鹿:そういう写真をどうやってつくんねんって感じですけどね。実験中という感じで。でも私は1週間後には全然違うこと普通に言ったりするから。気が変わってこっちの方が興味あるとか(笑)。常に楽しいほうへ行きたいし、「昨日よりも今日の自分のほうがいいやん、結構イケてる」ってほんまに思うんで、今の自分のほうを信じたいから、平気で変えられると思います。写真をやりはじめた頃から、自分でワクワクするものをつくりたいなっていうのはほんまに変わってないので。つくる基準ってそれだけですね。
――どんどん変わっていける。
赤鹿:自分の視点がいつも正しいとは1回も思ったことがないから、どこかの国に出かけたらまたひとつ視点が増えて、「こっちから見たらこうやけど、あっちから見たらこうやん」というのが増えるから。でも、美術ってけっこうコンセプトを求められてしまうじゃないですか。言い切らなあかんことが多い。日本語もたいがい特殊やなと思ってて、ひとつじゃない複数の感情とか、YES/NOじゃないグレーな部分が含まれていて、その日本語が自分をつくっている気もするし、グレーな日本語が美しいとも思う。がっちりしたコンセプトをしっかり伝えるって作品も素敵やけど、私がやると嘘っぽくなっていっちゃうんですよね。できひんこともないんやろうけど、年数を重ねて、言えてきちゃったりするのも怖いし。いっつもわかってないっちゃ、なんもわかってないんですけどね(笑)。
――完璧にわかりきるなんて、難しいですよね。
赤鹿:わかったら、もう辞めたらいいですもんね(笑)。ただ、オープンではありたい。分野で分ける必要もないと思うし、別に私が明日から役者になったっていい。なんでも積極的にやりたいです。必要なことはちゃんと選びたいけれど、なんか予感がしたらチャレンジしたい。
――お話を聞いていて、赤鹿さんにとっては写真を通じていろいろと考えていくこと自体がすでに大きな意味となっているように思えました。作品として発表するのは必ずしも必要なことではないと思いますか?
赤鹿:釣りが好きな人は釣りをしたらそれだけで楽しいし、それで終わりじゃないですか。それでいいのに、なんで発表するんかなっていうのは最近も思ってたんですけど。私はわりと内向的で、写真をやってなかったらあんまり外に出てなかったと思うんです。写真があることで、人とつながってこれたと思う。ひとりでいるのも好きではあるんですけど、「人とつながっていたい」とか「ひとりになりたくない」っていうのも絶対どこかにあって。発表するっていうことは、そういう関わりのことかなとは思いました。それぐらいしか私には方法がないかなと思うんですよね。
――すごくたくさんの出会いのなかで作品をつくられているように見えます。
赤鹿:そうですよね。(出会いは)多いような気がします。まだまだいろんな人に会いたいですけどね。跳ね除けたら、もったいないじゃないですか。できるだけ開いた状態でいたいと最近常々思ってるけれど、なんか結構怖いと思われてたりするんですよね(笑)。つくるものがちょっと怖いっていうか、すごい“私”っていう感じやからかな。
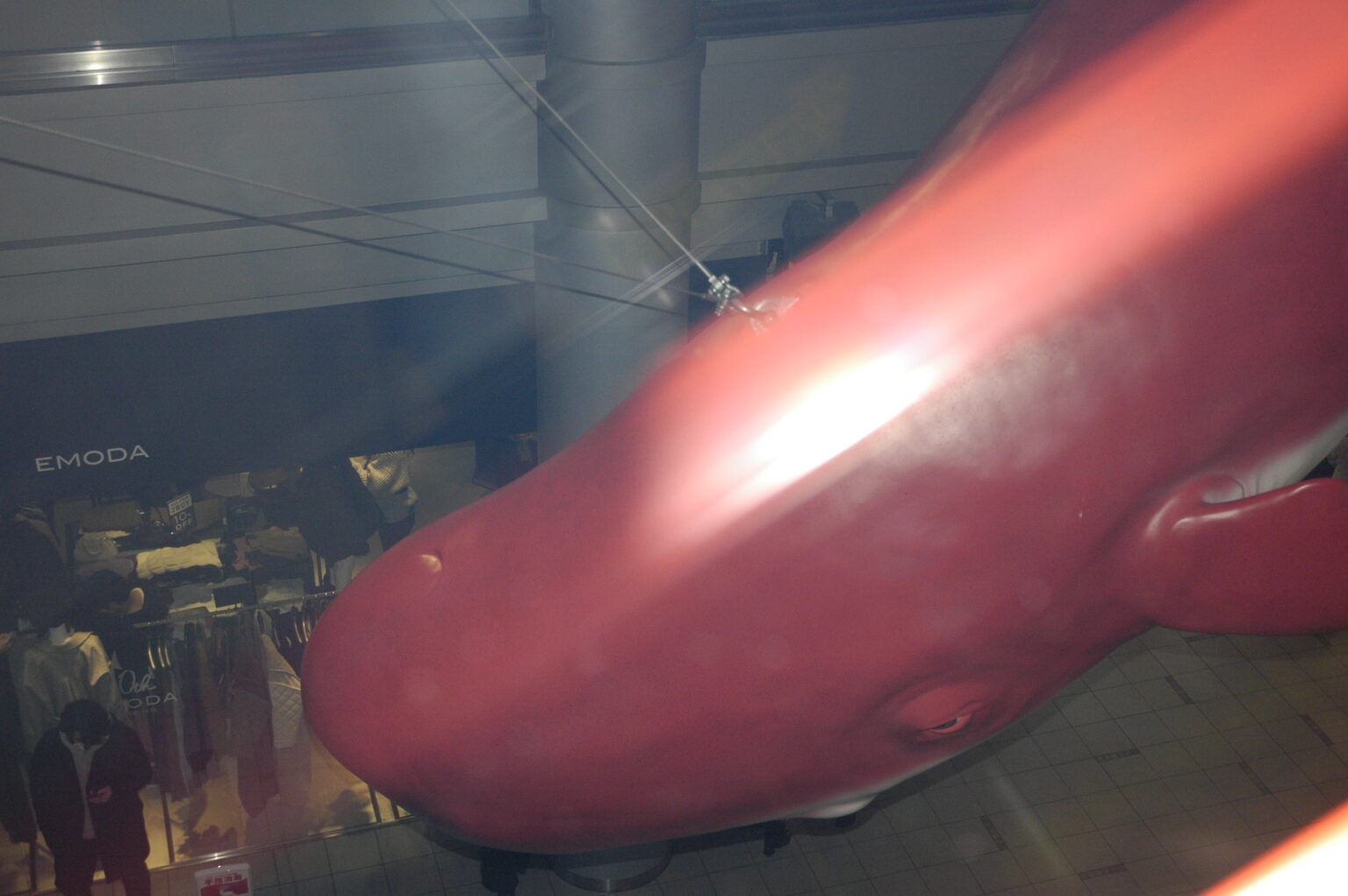
赤鹿:バイト時代の友だちとかずっと仲良いですよ。なかにはアートとかめちゃ難かしいもんやと思ってしまってる子もいますけど。私の作品とか、みんな興味ないと思います(笑)。私のつくってる姿には興味持ってくれるけど。モデルになったのに、その写真の仕上がりにも行方にも興味なかったりしますもん。「次ごはんいつ食べる?」って誘うだけで、それがいいかなと思いますね。なにもつくってなくても友だちというか。
――先ほど、大学時代になんで写真部を選んだんだろうというお話がありましたが、写真部を選んだ経緯はどんなものだったんですか?
赤鹿:中学、高校とソフトテニスをめっちゃやっていたんですよ。弱いチームながらも本気で。スポーツ好きやったんで、そのまま大学でもやってもいいじゃないですか。ただ、なんか当時筋肉を減らしたいと思ってたんですよね(笑)。年頃やったから恥ずかしい……。日に焼けてめっちゃ短髪とかで。制服のかわいいリボンと合わなさすぎて。「もう筋肉とはおさらばや!」と思って。テニス部時代も高校生ながら『VOGUE』とか読んでたんですよ。特に意識せず、本屋で「こんなんいいなー」とか思いながら。大学入って文系のクラブに行っちゃおうかと思って美術部とかも見たんですけど、たまたま写真部がパンキッシュな人から鉄道オタク系までいて、カラフルだなあと思って。いろんな人がいて、部室が居心地よさそうな空間に見えて。それで写真部に入ったのがスタートです。
――その頃はどういう写真を撮ろうと思っていたんですか?
赤鹿:『VOGUE』の広告みたいな感じに憧れてたんですよね。つくり込む世界。ここじゃないどこか。つくるならそんなんがいいと思ってて。それは写真部入った時点からで、部員のみんなで写真を見せ合う日とかあるんですけど、みんな花とか撮ったり、そんなんじゃないですか。でも私はその時からセッティングしてモデルになんかやらせてみたいなのを撮ってたから。はじまりから「普通のはなんかちがう」と思ってたんですよ。それはずっとですね。日本の景色とか、山を見たりしてもときめかなかったんやと思います。綺麗やなとは思いますけど、つくるならイメージして、創造する方がワクワクするなと思って。そういう作品を先輩に褒めてもらったこともあって、「写真やったらなんかできるかも」と夜間の専門学校(ビジュアルアーツ専門学校)に入りました。
――(この日カメラマンを務めた辺口芳典さんから)ひとつ質問なんやけど、赤鹿さんにとって「価値観が変わったとき」ってどんな瞬間やったんかなと思って。
赤鹿:価値観が変わったときか。2回あるかな。台湾にレジデンスで滞在して制作したときにな、それまで夢の話の作品のことをずっと、5年ぐらい考えてて。「景色が自分のものになる日」[※「Be my landscape」(2017年)]っていう作品を、人の夢の話からそういうタイトルをつけて、日本ですでにつくり終えててん。ソフトクリームを川から流して女の子を座らせて、その空間のなかで「景色があなたのものになったよ」っていう、そういう写真をつくっててん。それで、台湾に行ったときに、黄色い花の野原みたいなんがあって、観光名所みたいなとこやってんけど、みんなが黄色い花をバックに自撮りをしてんねん。それがめっちゃ綺麗な光景やってん。「あ、これ『景色が自分のものになる日』やん!」って思って。「自分がイメージしてつくったものよりいいものがちゃんと現実にあるやん」ってなった。それは自分を手放した瞬間やったかな。「こうやって私は今まで見過ごしてきてたんやな」「言葉さえ持ってたら、それにぴったり重なる景色に出会えるやん」っていうのが1回目。でもそこから「じゃあ、私なんでわざわざつくろうとしてんの」ってまた難しくもなってんけど。

赤鹿:2回目は、学校で「オープンスタジオ[※「赤鹿麻耶のオープンスタジオ」(2016年)、「赤鹿麻耶のオープンスタジオvol.2」(2020年)]っていう場を開いて、つくった写真を出来上がったものから壁に貼っていくようなことをしていて。そのときも夢の話で悩んでいたんですけど、「柔らかいすべり台」っていうテーマで(作品を)つくっていたんですよ。「むずいむずい、できんなあ」「ほんまにでっかくて柔らかいすべり台をつくらなあかんのか?」とか思ってて(笑)。その夢を見た友だちが言うには「生暖かくて、口のなかみたいやった」と。「でもその感覚をどうやってつくるんやろ」とか悩んでいましたね。オープンスタジオに貼ってあった写真のなかにピンク色の壁を押す女の子が映ってるのがあってんけど、たまたまお世話になってる学校の先生が来て、それを見て「これも“柔らかいすべり台”に見えるけどなー」と言ってくれて。その時に衝撃を受けましたね。意図したわけじゃない写真が、見る人が想像力を使ったらそういうふうに見えるんやと。「私、いつもなにを大事にしすぎてるんやろう」と思って。それも自分を手放した瞬間でした。
――自分を手放したときが、赤鹿さんにとっての“価値観が変わったとき”なんですね。
赤鹿:「すべり台じゃなくてもすべり台でいいんや。これがすべり台と思ったらそう見える人がいんねや」と思って。そういうのをたまに人から言われてハッとする。「なにやってたんや今まで」とか「今までやってきたこと無駄やん」みたいな、今までの苦労を全部消される感じやねんけど(笑)。「WALKEDIT」もそうやけど「こんなんでよかったんちゃうの?」みたいな。自分が悩んだものほど、人の心を動かしてない感じもわかるんよ。感動しづらいんやと思うねん。というか、自分がすごくつくり上げた写真は、人の人生と関係なかったりするから。たとえばこのコーヒーカップを撮ったら、それはみんなの日常に関係してくるやん。豚を連れてきて一緒に写真撮ったりしても、それはみんなの日常に寄り添わない(笑)。でも、そこはずっと戦い続けなあかんねんな。つくらなくていいのにつくって、それで誰も心動かへんかもしれへんし。エゴ的な写真と普通の写真との間で考え続けるんちゃうかしら。

インタビューのなかで繰り返し語られた“手放す”という言葉。自分のエゴを手放し、フラットな気持ちで制作ができたら確かにそれが一番自然なのかもしれない。でも、赤鹿さんに“手放す”瞬間が訪れるのは、絶えず自分と写真との距離について考え続けているからこそなのだと思う。
自分のエゴと向き合い、写真がわからなくなるところまで考えた先で“手放す”瞬間とふいに出会う。そしてその瞬間が赤鹿さんの写真観に新鮮なものをもたらし、新しいチャレンジに向かう糧になっていく。そんなふうにどんどん変化していく赤鹿さんの写真がこれからどうなっていくのか、楽しみに待っていたいという思う。

1985年、大阪府生まれ。2008年関西大学卒業。10年ビジュアルアーツ大阪写真学科卒業。2011年、作品《風を食べる》で第34回写真新世紀グランプリ受賞。大阪を拠点に海外を含む各地で個展、グループ展を開催。夢について語られた言葉、写真、絵や音など多様なイメージを共感覚的に行き来しながら、現実とファンタジーが混交する独自の物語世界を紡ぐ。
スズキナオ / Nao Suzuki
東京出身、大阪在住のフリーライター。「デイリーポータルZ」等のWEBサイトを中心にコラムを執中。大阪のミニコミ書店「シカク」のスタッフでもある。著書に「深夜高速バスに100回ぐらい乗ってわかったこと」「関西酒場のろのろ日記」「酒ともやしと横になる私」など。
INFORMATION
会期:前期 2021年2月25日(木)~3月22日(月)、後期 3月24日(水)~4月19日(月)
時間:11:00~20:00
企画制作:Happenings
協力:キヤノン株式会社、ホテル アンテルーム 京都、まちじゅうアーティスト事業








