ここ数年、年間100作品くらいテレビドラマを観ている。もちろん、それぞれの作品全話を観通しているわけではない。
ここでいう「テレビドラマ」は、主に日本国内におけるテレビの地上波/衛星放送を想定してつくられた、複数話からなるドラマのことを指している。最近では、TVerやNHKプラスなどのテレビ配信サービス、Netflixなどのオンライン映像配信プラットフォームの登場により視聴環境も多様になってきた。また、オンライン映像配信プラットフォーム限定ドラマやスマホ視聴を想定した縦型ドラマも増えてきた。それを踏まえ、ここでは「テレビドラマとは」を厳密に定義することは避けたい。
ただ、逆に言うと、(語義矛盾だが)テレビドラマが「テレビだけのもの」でなくなったことで形式にも工夫が生まれた。また後述するが、とにかく3ヶ月ごとにどんどん新しい作品が生み出されるので、(その弊害ももちろんあるため手放しには是としづらいところもあるが)社会的な状況が色濃く反映されやすい点も興味深い。わたしがテレビドラマを精力的に観はじめたきっかけはTVerの存在が大きいが、観続けている理由はそうしたテレビドラマの特殊性によっている。
ちなみに、テレビドラマを観るときにわたしが注目するのは、原作の有無と、ドラマの設計図とも言うべき脚本だ。いつもテレビドラマを観たときには、タイトルと放送年と放送局、脚本家を記録して所感を残している。最近はテレビドラマの記録用にnoteもはじめた【ニッポンのドラマ】。
この記事では、わたし自身の経験を交えて、「テレビドラマと社会」について書いていきたい。
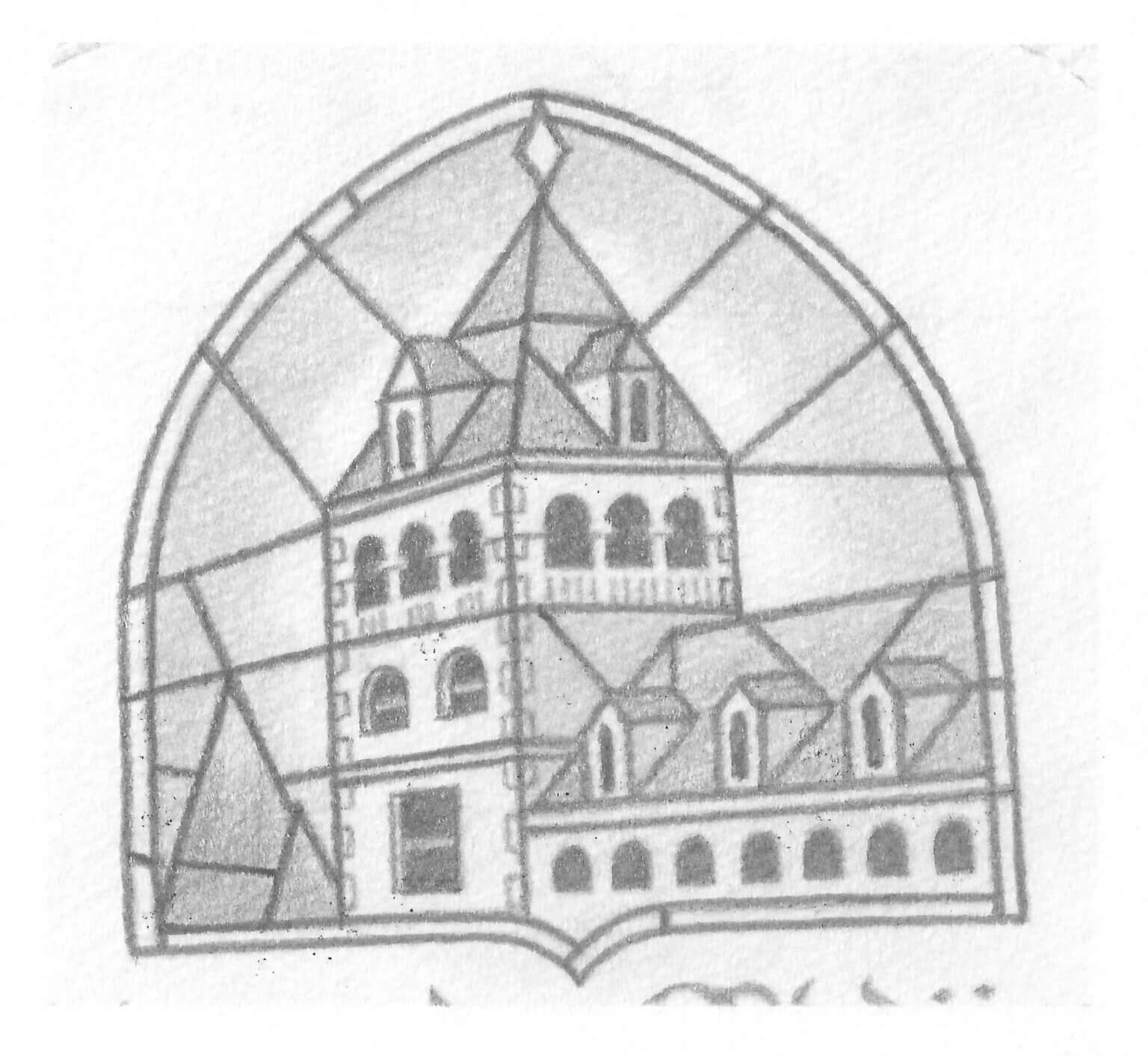
1990年代以降のテレビとの付き合い方
本題に入る前に、わたしとテレビとの関わりについて、物心つきはじめた90年代からざっと遡ってみたい。
1984年愛知県生まれのわたしにとってテレビドラマは結構身近で、小中学生の時期には「ひとつ屋根の下」[1993、フジテレビ、脚本:野島伸司/榊原小3]、「家なき子」[1994、日本テレビ、脚本:高月真哉・いとう斗士八/榊原小4]、「ふたりっ子」[1996、NHK、作※:大石静/榊原小6]、「聖者の行進」[1998、TBS、脚本:野島伸司/榊原中2]など、クラス全員が観ていたのではないか?というくらい、みんながテレビドラマを観ていた。インターネットもまだ大して普及していなかった地方の子ども(男性)にとって、娯楽は野球かテレビくらいしかなかった時代の話である。
※連続テレビ小説シリーズは基本的にオリジナルドラマだからなのか、「脚本」ではなく「作」として脚本家がクレジットされる
2000年代にもなるとインターネットがどんどん市民権を得ていく。それに伴い、テレビの視聴時間をネットに費やすようになった。2002年日韓ワールドカップの頃は高校3年生で、ひとなみに受験勉強に勤しんでいたので(その時期だけサッカーには浮かれていたものの)、テレビドラマを観ることも少なくなった。決定打は、大学入学。当時2003年以降、テレビを持たない生活に入る。
インターネットとテレビドラマ
いつの頃からか具体的にはよく覚えていないが、2009年の著作権法改正でネットに無許可でドラマをアップロードすることが違法になっている。しかし、当時はWinMXやらWinnyやら、YouTubeやらbilibiliやらでネットに違法ドラマが溢れるようになる。
そんな最中の2013年には連続テレビ小説「あまちゃん」[2013、NHK、脚本:宮藤官九郎]が放送される。あまりの面白さに、家の近所の電気屋でテレビを買い、配達してもらう時間が惜しいのでそのまま自転車で持ち帰ったことを思い出す。年末の紅白歌合戦での展開も含めて、このテレビドラマは、いまだにわたしにとっての金字塔だ。
ただ、テレビドラマウォッチにおいて革新的だったのは、冒頭でも名前を挙げた、2015年に公開されたテレビ配信サービスTVerだ。インターネットで公式に、しかも全国のテレビドラマが観られるようになった。先述の通り、近年ではTVerのみならずNetflixやU-NEXTといったオンライン映像配信プラットフォームと連携してテレビドラマが配信されるようになった。
このようにしてテレビドラマは、テレビだけのコンテンツではなくなっていった。
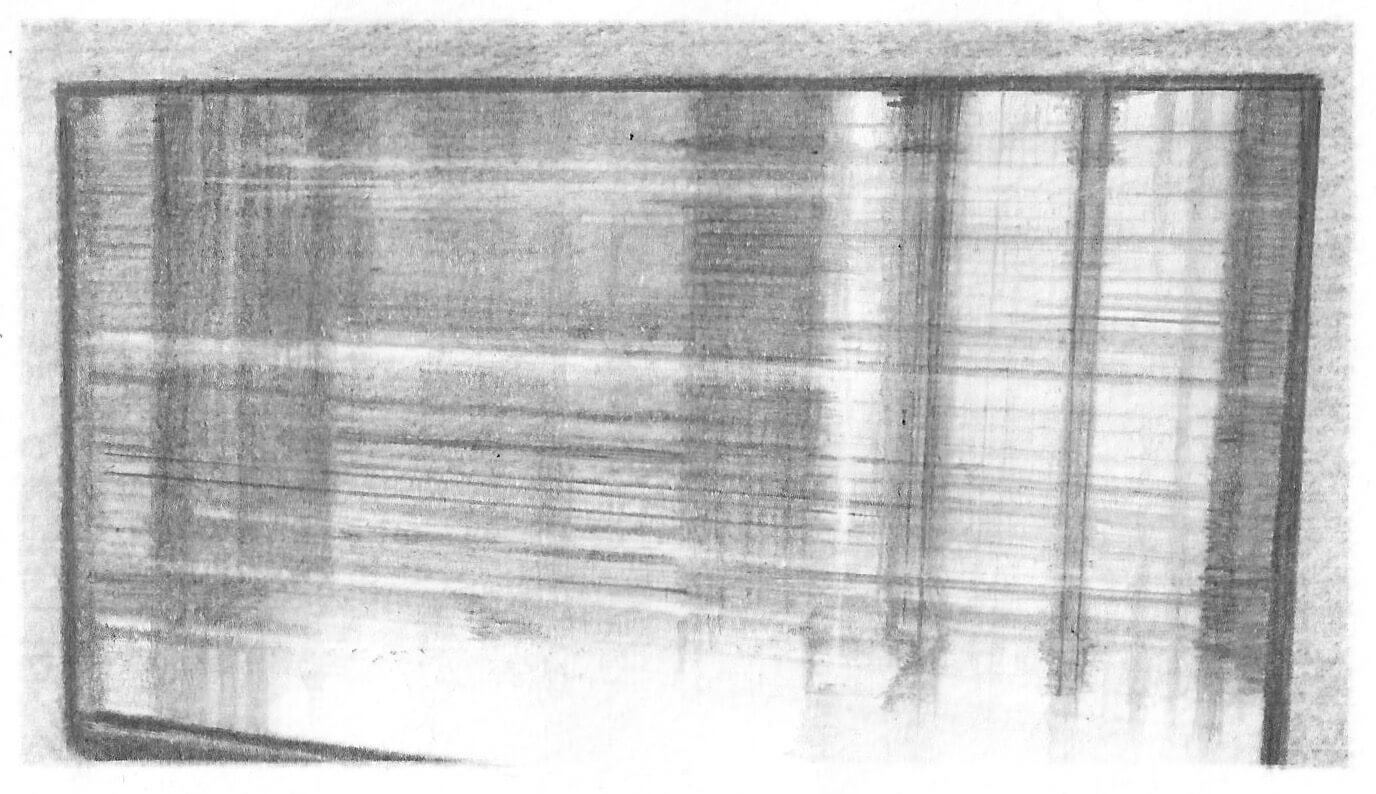
テレビドラマと社会
ではここから、テレビドラマそのものについて書いていきたい。
テレビドラマの大きな特徴のひとつは、その大半が1年を4つの時期に分けた「クール」ごとにつくられている、ということ。毎年毎クール、おびただしい量のテレビドラマが制作、放送されている。そしてその大半は、マンガか小説の原作があるものだ。近年は、原作がなくテレビドラマオリジナルという作品は珍しくなっている。このトピックについて掘り下げはじめると、それはそれで込み入ってくるので、この事実を指摘するにとどめておきたい。
ちなみに、膨大にあるテレビドラマのなかでも最後まで観続けられる作品には、適切な「推進力」がある。また、そこには「問い」と「世界観」、そして、その「世界観」を魅力的に描くためには「バディ(仲間)」の存在が不可欠だ。すべての「いいテレビドラマ」は「バディもの」であり、その世界観をよりよくするものが優れた「問い」だ、というのがわたしの仮説である。
ともあれ、わたしは毎クール20本近くのドラマをひとまず1話目くらいは観るが、文字通り、手をつけ切れないほどのテレビドラマが放送されている。そして「群」としてテレビドラマを見てみると、世相がわりと反映されているということがわかる。
近年のテレビドラマの特徴
近年のテレビドラマの特徴をまずひとつ挙げると、社会的な要素がしっかり描かれていることだ。たとえば、LGBTQの視点が自然と導入されている作品(良作を挙げると「おっさんのパンツがなんだっていいじゃないか」[2024、東海テレビ、脚本:藤井清美]や、現代の若者の貧困や闇バイトといった社会的な課題を取り上げるテレビドラマも多い(「3000万」[2024、NHK、脚本:弥重早希子・名嘉友美・山口智之・松井周]など)。とりわけ近年よく見られるのは、SNS上での誹謗中傷を重く取り上げる姿勢だ(たとえば「しょせん他人事ですから~とある弁護士の本音の仕事~」[2024、テレビ東京、脚本:小峯裕之]など)。これは10年以上前のドラマでは描かれていなかった視点だと言っていい。
一方で、「無知な女性をワケ知り顔の男性が教える」という旧世代を引きずっているような構図が、現代のテレビドラマでもたびたび見られる。また、障害者に焦点を当てた「silent」[2022、フジテレビ、脚本:生方美久]の大ヒット後、障害者が登場するドラマがしばらく継続するという、本来流行にすべきでないことが「流行」のように見えてしまうこともある(そのなかでも観るべきは「パーセント」[2024、NHK、脚本:大池容子])。すべてがアップデートされているわけでは当然ない。
また、脚本家によっても背景となる社会や登場人物の描き方は変わるため、十把一絡げにはできないが、「社会的な課題をテーマにしてテレビドラマをつくる」という流れから、「ストーリーの設定に社会的課題と密接に関わる要素が入っている」といった流れになっているようにも感じる。前者は野島伸司や坂元裕二が手がける作品に象徴的で、後者は野木亜紀子や生方美久が手がける作品に象徴的だ。
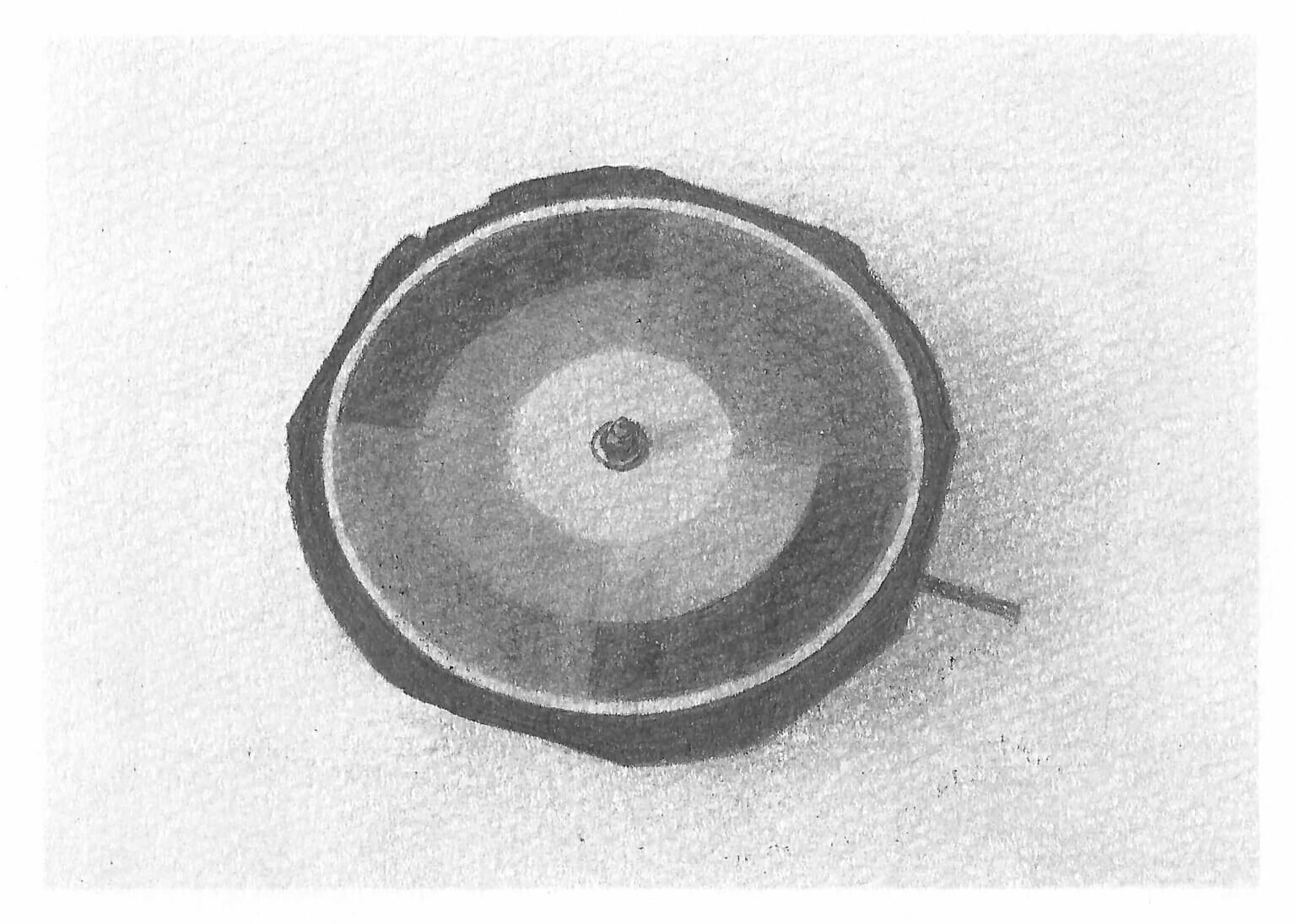
条件としての社会的課題
「3年B組金八先生」を1970年代から2000年代まで通して観ると、校内暴力からいじめ、学級崩壊と学校をめぐる「課題」が変遷し、2000年代以降はドラッグや「裏サイト」といったトピックスが描かれる。「社会的な課題をテーマにして」というのは、まさにそういう取り上げ方をイメージしている。
一方で「ストーリーの設定に社会的課題と密接に関わる要素が入っている」と書いたのはどういうことか。その好例として挙げたいのが、「東京サラダボウル」[2025、NHK、脚本:金沢知樹]だ。
黒丸による同名マンガを原作にしている本作は、女性刑事である鴻田麻里と警察通訳人である有木野了を主人公に据えている。日本に生き、容疑をかけられている外国人役の登場人物が多くあらわれるわけだが、社会的な課題としての外国人犯罪そのものがテーマになっているわけではない。外国人が異国としての日本に住み暮らすなかでは、日本人として育った者には見えづらい「壁」がさまざまにある。このドラマは、刑事と通訳人という視点を借りて、その見えづらい日常を炙り出そうとする。
言うなれば「対象としての社会的課題」から、「条件としての社会的課題」にうつっているとも言えるだろうか。厳密にはテレビドラマではないが、野木亜紀子が脚本をつとめたWOWOWドラマ「フェンス」[2023、WOWOW、脚本:野木亜紀子]もそうした条件として社会的課題をとらえている好例だ。沖縄を舞台に、基地問題や米兵による暴力事件を直接の対象とするのではなく、われわれの社会を条件づける要素として、しっかりと描いている。
当然ながら現代の(昔もだろうが)社会的な課題は単一的なものではなく、一つひとつが複雑に入り乱れている。そうした状態を誠実に伝えようという意識が、「条件としての社会的課題」という取り扱い方にあらわれているとも見ることができるのではないだろうか。
書こうと思ったけど書ききれなかったトピックス
最後に、「書きたかったけど書けなかったトピック」を紹介して終わりたい。
・テレビドラマとインターネットの関係。最初の方にかいつまんで書いただけでも、近過去の歴史においても厚みある部分なのではないかと感じた。このトピックをしっかりと調べて丁寧にひもといていくと、90年代以降の日本のメディア史の解像度がさらに上がるのではないだろうか。
・2000年代以降のテレビドラマ。冒頭で挙げそびれたが、愛知県では「お金がない!」[1994、フジテレビ、脚本:両沢和幸・戸田山雅司]が2000年以降も頻繁に再放送されていた。榊原があまりテレビドラマを観なかった時期のテレビドラマにもあたってみたい。名作の誉高い過去のテレビドラマも今観返してみるとぼんやりした作品でしかなかったということもなくはないが、それはそれで時代が見えてきて興味深い。
・テレビドラマ制作現場における問題。先に「最近では原作のないドラマは珍しい」という旨を書いたが、原作者と脚本家との齟齬が大きくなり、社会問題化して最終的には原作者の死につながってしまったという痛ましい事件が2024年に起きた。作品をつくる現場に対して、テレビドラマファンに何かできるわけではないが、優れた取り組みにはぜひ賛同の意を表したい。
・そのひとつとして、共同執筆形式の脚本制作プロジェクト「Writers’ Development Room」の取り組みには期待したい。言及した「3000万」はこの形式で進められた。テレビドラマの可能性を広げるだけでなく、脚本家の働き方についても影響を与えうるものだと思うので指摘しておきたい。
・「医療もの」と「不倫もの」の異常な多さ。日本のテレビドラマでは、医者や病院をテーマにした、いわゆる医療ものの作品が毎クール必ずといっていいほどつくられていることに気がつく。よくよく考えると、この状況は普通ではない。また、不倫もののテレビドラマも絶対になくならない。近年はセンセーショナルなタイトルのドラマも増えたように感じる。
・最後の最後に。すべての「いいテレビドラマ」は「バディもの」であり、その世界観をよりよくするものが優れた「問い」だ、というわたしの雑駁な仮説をもう少し精度の高いものにしたい。
榊原充大/Mitsuhiro Sakakibara(株式会社都市機能計画室)
1984年愛知県生まれ。2007年神戸大学文学部人文学科芸術学専修卒業。建築や都市に関する調査・執筆、提案、プロジェクトディレクション/マネジメントなどを業務としプロジェクトの実現までをサポートする。2008年から2023年まで建築リサーチ組織「RAD」を共同運営。2019年に、公共的な施設の計画や運営のサポートをおこなう「株式会社都市機能計画室」を設立。2019年〜2020年、アート複合施設「Super Studio Kitakagaya」開設ディレクションサポート。







