食、身体、医療などのテーマから人間の生に焦点を当てる人類学者・磯野真穂を迎え、本特集の共同編集者・小田香との対談を収録した。これまで、他者の言葉や行為と向き合い、人類学の間口を拡げてきた磯野は、小田の映画になにを見たのか。互いに異なる世界の触知を確かめながら、視座を通じ合わせていく。
収録:2021年8月9日(月)ZOOMにて
DIALOGUE:小田香×磯野真穂|私は理解したいし、理解されたい(理解できないけれど)
1 「誰かを殴ったことがありますか?」
2 「物語のほうがよっぽどノンフィクション」
>>記事を読む3 「言葉にすると陳腐だけど、いかに知らないかをわかること」
4 「それって、聞くことの本質的な業だと思う」
5 「傷つけ合ったっていいやん」
>>記事を読む6 「絶望しか感じられないですよね」
7 「お互い変わらないんじゃないかな」
>>記事を読む
1 「誰かを殴ったことがありますか?」
磯野:はじめまして。お伺いしたいことがたくさんありますが、さっそく作品の話から伺っていきたいと思います。『あの優しさへ』に出てくる「私はカメラで殴ったんじゃないか」という言葉が印象的でした。でも、カメラはある種の媒介でもあるので、カメラがご家族と小田さんの間でクッション(緩衝)にもなっていたんじゃないかなと思いました。そこで、ひとつ目の質問です。小田さんは、媒介がないところ、カメラのないところで、比喩的にでも誰かを殴ったことはありますか?
小田:家族を、もしくは人間をってことですか?
磯野:手で殴ったってことじゃないですよ(笑)。私たちは日常のなかで互いを傷つけ合わないために、たとえば言葉を工夫したりしています。小田さんの場合は、その役割を多少なりともカメラが果たしているんだと思って。だから、カメラを媒介にしない状況で、他者と遠慮なしに殴り合ったようなことはあるのかなと。
小田:今思い出す限りではないです(笑)。嫌なことを嫌なこととして受け止めることはもちろんありますが、そんなとき、私は黙っちゃうんですよね。
磯野:なるほど。カメラがあるからこそ、ぎりぎり踏み込めるところもあるんですかね。
小田:たとえば、コミュニケーションのなかで互いを理解するために傷つけ合うというプロセスがあっても、私自身は一歩引いちゃうんですね。でも、カメラがあると、自分にパンチが入ってくる前に、パシッと受け止められる感じ。良くも悪くもいやらしいところだなと思うんですけど、たぶんカメラを使っているんだと思います。なにかしらの隠れ蓑として。

磯野:なるほど。小田さんの作品を拝見して、現実をわかりやすくすることに対する抵抗があるのではと感じました。たとえば『ノイズが言うには』も、家族の会話がスクリプトの一部だったり、撮影している光景をさらに後ろから撮っていたり、家族の関係性をあえてぐちゃぐちゃに見せているのかなと。「わかりにくくしたい」という意図ではないと思いますが、あえてストーリーをつくらないことを意識されているんですか?
小田:普段、撮影中はなにも考えないですね。処女作の『ノイズが言うには』は例外ですが。最新作の『セノーテ』の場合は、人に会い、撮ることで、自分がなにを聞いて、なにを見ているのかに向き合っています。これも「撮影」という行為を使っていると言えますが、神話や神秘的なものに対する固定観念が撮影することで分解され、ちゃんと小さい単位に戻っていくんですよ。「わかりにくくしたい」という意図ではないですが、経験的には、実際に撮ったものを卓上に並べたとしても、わかりやすいものは浮かび上がってこない。撮影の過程で、一般論や鑑賞者をひとつの方向に導いていくような答えのある体験をしているわけではないから、そういうものはつくれないというか……。

磯野:これ、アーティストと研究者の違いかもしれませんね。人類学も不可視なものを見ようとする学問なんですけど、人類学者はそこになんらかの人間の普遍性みたいなもの、照らし出されるものを見出そうとする。それはある種の傲慢、暴力性を孕む行為だけど、それを知りながらもそこに届こうとすることに価値を見出しているところがあると思うんですね。断片的になると伝えられないものもあるので、私は「わからないこと」の先で、自分自身がわかるところまで徹底的に求めていくんです。それについてはどうですか?
小田:「わかること」と「伝わること」は違うものだと思います。でも、私が感じたもの、世界のどこかにあるものが、目をとおして伝わってほしい気持ちはある。そのとき、「これはこうだ」と対象に言葉を与え、分類することの限界も感じるんですよね。もっと芸(技術)が身につけばできるようになるのかもしれませんが、今の自分の能力で無理矢理やってしまえば、軋みが生じるだろうと。
磯野:それは、『あの優しさへ』で「『寂寥』のようなものはもう撮れない」と言っていたことに通じているんですかね?
小田:どこまで責任を負えるか、ですよね。もちろん、人の人生に対して責任を負うことなんてできません。でも、責任を負いたいと思えるかどうか。一生背負っていくというのは大袈裟かもしれないけど、人間を、人の私生活を撮るとはそういうことだろうと思います。『あの優しさへ』の撮影時、それに驚いている自分がいた。だから、準備できていないと思ってしまったんです。
磯野:たしかに、小田さんの作品を拝見していると、正面から画を撮られていますよね。被写体であるセナッドさんの言いようのない寂しい眼が本当に伝わってくる感じ。カメラを向けられて、ああいう顔ができる関係性はどういうものなんでしょう。
小田:不思議ですよね。セナッドは英語を話さない人で、母国語はボスニア語なんです。私は英語を少し話しますが、ボスニア語は話せない。セナッドの家には1週間くらい滞在したんですけど、ほぼ身振り手振りでコミュニケーションをとっていて。カメラを構えれば「撮るよ」っていうことは伝わりますが、なんだろう……、セナッドが与えようとしてくれた気持ちが大きかったですね。


2 「物語のほうがよっぽどノンフィクション」
磯野:さきほど「責任を負うことなんてできない」というお話がありましたが、今はどうですか?
小田:どんなテーマで誰を撮るかによると思います。ドキュメンタリーなので、ひとりの人間を撮っていると、良い面だけでなく悪い面も見えてくる。それを撮ること自体は問題ないのですが、上映するとなると、難しさを感じます。彼らの生活もあるので。だけど、まるっと描かなければ欠落してしまう部分はあって。それらを映画的な方法でどうとらえることができるのか、挑戦していきたい気持ちはあります。
磯野:それについては、私も同じ悩みをもっていて。インタビューや観察でも人間の嫌な面が見えますが、そこは書けないんですよね。原稿を仕上げてみると、ただ良い人が登場し、悪い人はふんわりとした第三者、ある種、勧善懲悪的な物語になりがちで。
小田:対象の「悪い面」を書けない場合、研究対象になるのは「良い面」だけなのでしょうか?
磯野:倫理や守秘義務の関係で、登場人物が現実から離れた素晴らしい人になりがちなところはあると思います。拙書の『なぜふつうに食べられないのか』は、食べるとはなにかを追求した本なので、登場人物が良い人かどうかは関係ないわけですが、ある種の人間のもつ狡猾さ、本人にとっては書かれたら嫌だろうエピソードが2、3含まれています。もちろん許可を得て、匿名で書いてはいるけど、もしかしたらご本人は嫌だったかも。私も若かったので勢いで書いちゃったところもありますね。往々にして、人文科学の研究で「弱者」を描くと、どうも純粋に傷ついて権力に虐げられた人ということになりやすい。本当は人間ってもっとごつごつした生き物のはずなのに。その点でドキュメンタリーなのにフィクションになっているわけですよね。映画や物語などの創作のほうが、よっぽどノンフィクションだなと感じることもあります。

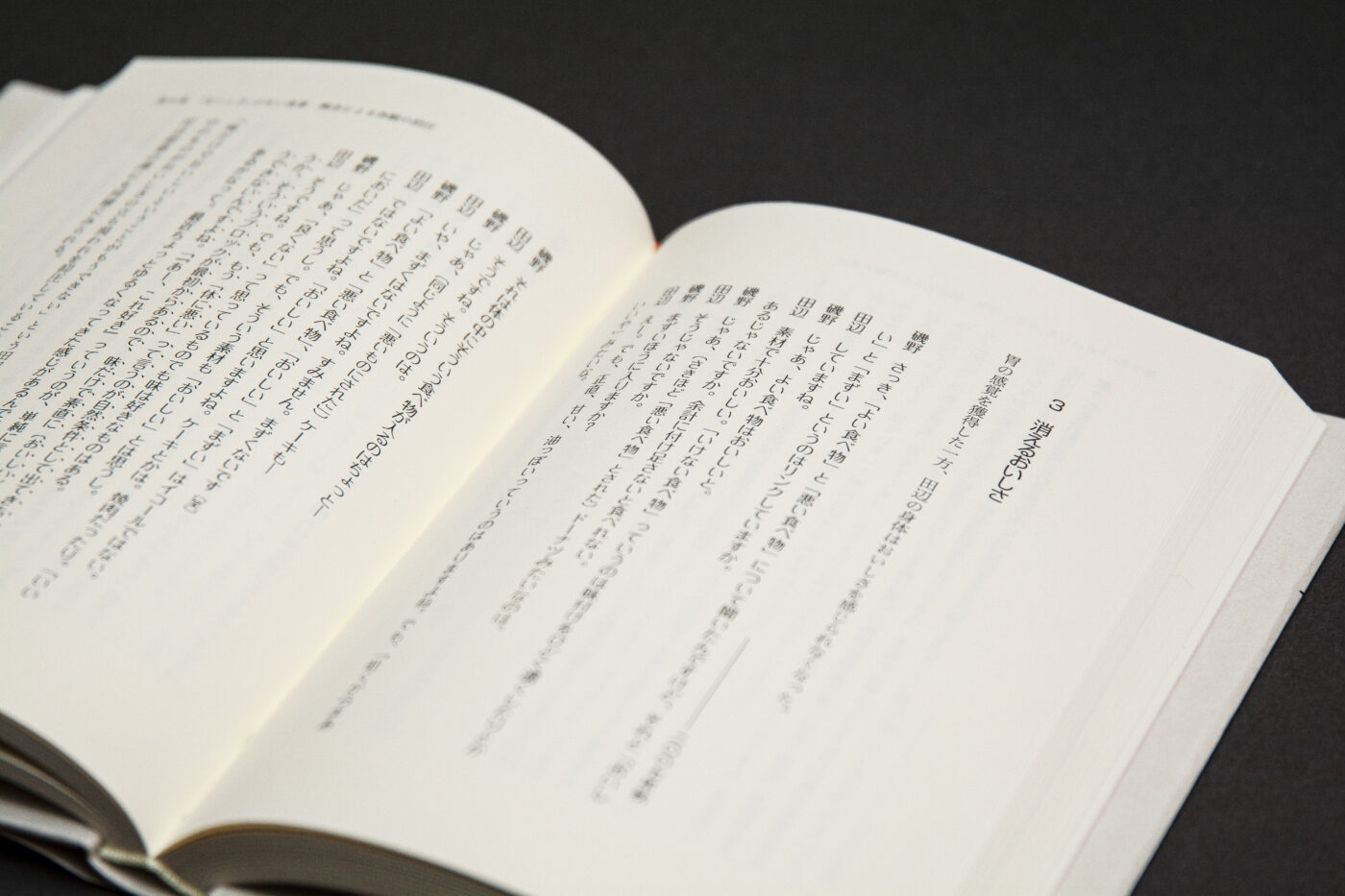
小田:私もそう思います。その点ですごいなと思うのが、アーティストの小森はるかさんと瀬尾夏美さんが手がけた『二重のまち』ですね。東北に住みながら震災以降の人々の暮らしや言葉を記録していて、それらを映像とテキストで語り直すことでフィクション化しています。映画のなかに描かれたのは、震災という大きな出来事を前に語ることができなくなっていた個人の小さな傷、しこりが癒されていく過程なんですけど、そこにたくさんのインタビューから浮かび上がった声のようなものが表出されていて。それはフィクションの力によるものだと思います。生々しすぎる痛みや個人の尊厳は守られながら、声となった本質が前に出てくるようにつくられている、とにかくすごい試みで……。フィクションのほうがある種のノンフィクションをまるっと描けるだろうというのは同感です。
磯野:小田さんの作品にも、『二重のまち』のようなフィクション化する手法を使ったものはあるんですか?
小田:『セノーテ』は、その過程への挑戦ですね。普通のドキュメンタリーとしての起承転結はなく、なにか自分が感じた本質、体験っていうのをどう語り直すかの実験だったんですけど。
磯野:「責任」という点に関しては、見たものを見たまま出すのも違うだろうと。私は学問をやっているので、私の考えをできる限り明瞭にして書きます。その言葉に対して、研究者として責任をとっていきたい。だから、『セノーテ』を拝見したとき、私がこれを文章で書いたらどうなるんだろうと考えました。小田さんが感じさせる本質を私ならどう伝えるのか……。
小田香 / Kaori Oda
1987年大阪生まれ。フィルムメーカー。
2016年タル・ベーラが陣頭指揮するfilm.factoryを修了。第一長編作『鉱 ARAGANE』が山形国際ドキュメンタリー映画祭アジア千波万波部門にて特別賞受賞。
2019年『セノーテ』がロッテルダム国際映画祭などを巡回。
2020年第1回大島渚賞受賞。
2021年第71回芸術選奨文部科学大臣新人賞受賞。twitter https://twitter.com/_kaori_oda
磯野真穂 / Maho Isono
独立人類学者。専門は文化人類学・医療人類学。博士(文学)。早稲田大学文化構想学部助教、国際医療福祉大学大学院准教授を経て2020年より独立。身体と社会の繋がりを考えるメディア「からだのシューレ」にてワークショップ、読書会、新しい学びの可能性を探るメディア「FILTR」にて人類学のオンライン講座を開講。著書に『なぜふつうに食べられないのか——拒食と過食の文化人類学』(春秋社)、『医療者が語る答えなき世界——「いのちの守り人」の人類学』(ちくま新書)、『ダイエット幻想——やせること、愛されること』(ちくまプリマ―新書)、宮野真生子との共著に『急に具合が悪くなる』(晶文社)などがある。
——この記事で紹介した磯野真穂の本
『なぜふつうに食べられないのか 拒食と過食の文化人類学』(春秋社、2015)
『急に具合が悪くなる』(晶文社、2019)






