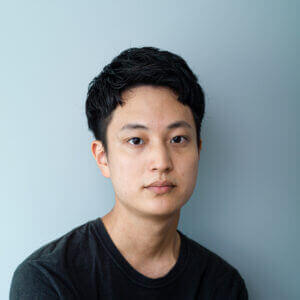2024年3月1日(金)〜3日(日)、代官山ヒルサイドプラザにて、contact Gonzoによる新作パフォーマンス公演が開催された。大阪を拠点に活動するcontact Gonzoが、東京都ならびに公益財団法人東京都歴史文化財団 アーツカウンシル東京が運営する「シビック・クリエイティブ・ベース東京[CCBT]」の2023年度アーティスト・フェローに選定されたことがきっかけだ。
身体の接触や衝突を軸に作品制作を行うcontact Gonzoが、今回のテーマとしたのは「皮膚/スキン」。外からの情報を微細に受け取るセンサーでありながら、情報を自ら発信するインターフェースでもある皮膚に着目し、パフォーマンス内で感じる痛みや衝撃の感覚を、鑑賞者にも共有することを目指すという。皮膚にまつわるリサーチの過程がDiscordで公開されるなど、実験的な試みが展開された今回の公演では一体、何が共有されたのだろうか。筆者の体験をレポートしながら、考察してみたい。

ヒルサイドプラザの地下闘技場
螺旋階段を下って、洞窟のように薄暗いギャラリーへと進む。左手に並ぶ作品たちを横目に、右手から下を覗いてみると、真っ黒いリングが現れる。ロープのないリングのまわりを観客が取り囲んでいく。
contact Gonzoのメンバー4人(塚原悠也、三ヶ尻敬悟、松見拓也、NAZE)が入場してくる。衣装にはNIKEやMonster Energyをはじめとするブランドがならぶものの、それらはすべて裏返されて、ツギハギにされている。その風貌はどこにもないエクストリームスポーツ選手のようでありながら、地下闘技場に集まるゴロツキのようでもある。縦長の電光掲示板を背負った津田和俊がリングの周囲を巡る様子からも、どこか退廃的な未来を思わせるムードが漂っている。

ひとりがおもむろにペットボトルを放ると、スピーカーから「わーいわーい」という声が聞こえてくる。ペットボトルが宙を舞っては、ボトンと落ちる。ゆっくりと繰り返し続ける、一見すると無意味にも思える行動は、動物たちの手遊びのようだ。
しばらくして、手馴しが終わると「試合」がはじまる。はたきあいやどつきあい、ときには上から乗っかり、ときには走って体当たりする。互いの動きを真似しあっていたと思えば、まったく別の動きが差し込まれ、元あった動きはどこかへ消えている。お決まりのようでいて、お決まりではない。喧嘩のようでいて、喧嘩ではない。秩序と無秩序が同居しているような光景はどこかおかしくて、観客の間ではときにドッと笑いが起こる。contact Gonzoが探求してきた即興的な身体の衝突によるパフォーマンスが繰り広げられていく。

ただし、これまでと異なるのは、パフォーマーたちの身体に装着されたオリジナルデバイスだ。このデバイスは今回の公演のために制作されたもので、人と人との接触やその速度・圧などの情報を電気信号化するセンサーが仕込まれている。信号は変換され、リングの下に設置された8台の巨大な重低音スピーカー(Function One)から、音圧となって会場中に伝わる。会場に鳴り響く鈍い音に、リングを取り囲む観客の一体感は増していく。技巧的でも派手でもないように見えるぶつかりあいにもかかわらず、プロレスのような祝祭感すら生まれていた。ほとんど触れられるどころか、ぶつかってしまいそうなくらいの距離で巻き起こる場外乱闘もまたその印象を強くしていた。
ナンセンスの穴
自己アイロニー(=自己ツッコミ)と自己ユーモア(=自己ボケ)を遊び心たっぷりに操作することで、習慣化してしまった自分のあり方を自己破壊する。
自分に対して、自分でわざと、もうひとりのキモい自分を言語的に作り出す。
あなたのこれまでの人生を、たんなるお約束(コード)によって展開しているお決まりのおしゃべりみたいなものとして捉えてください。自分に飽きてしまっている状況があるのだとしたら、そういう人生をアイロニーとユーモアによって転覆し、別の豊富な可能性を、言葉によって、言葉遊びによって考えるのです。
引用:千葉雅也著『勉強の哲学――来たるべきバカのために』文藝春秋(2017年)P.76
*太字は原文ママ
はたきあいにどつきあい、体当たりに押し合いへし合い、ときにはビンタを真正面から受けたと思えば、別の人にもビンタを受ける。流れるように身体接触のコードが変わっていくパフォーマンスを見ながら、上記の千葉雅也による論を思い出した。

言葉と欲望の視点から、勉強を原理的に読み解きなおし、深い勉強の実践を指南する本書では、置かれた環境のコードを疑って批判する「ツッコミ=アイロニー」、コードに対してズレようとする「ボケ=ユーモア」が分析概念に用いられる。そこでは自分が慣れた環境のコードから離れ、「自由」になるために、アイロニーやユーモアを用いて、言語偏重になることで、「変身」をしていくことが目指される。
一見、無関係の論にも思えるが、会場で配布されたフリーペーパー『The Skinland Times』に掲載された塚原による小説では、数百年をかけて人類の発話量が次第に減少した2700年代の世界で、皮膚の接触によるコミュニケーションが発達した様子が描かれていた。ならば、千葉の論における「言語」の部分に、「身体」を代入してみてはどうだろう。
contact Gonzoのパフォーマンスでは、ついさっきまであったコード(たとえば誰かがビンタをしたら、同じようにビンタをし返す)が、いとも簡単に転覆され、次の瞬間には、別のコード(たとえば体当たりをした人に誰かが乗っかれば、さらにまた別の人が乗っかっていく)が出現している。そのコードもまたすぐに転覆され、消えていく。人の身体接触の方針を切り崩すアイロニーと、別の身体接触を差し込むユーモアが次々と展開していく。
同書では別の可能性へと開かれるための段階として、「現実に密着した道具的な言語使用」から、「言語をそれ自体として操作する玩具的な言語使用」とウエイトを移すことが推奨される(PP.49-53)。思えば、私たちは普段、何かを達成するための目的的な身体使用をしている。それらが達成される限りにおいて、私たちは自身の身体=道具を意識しない。しかしcontact Gonzoのパフォーマンスでは、それらが自ずと解体され、身体は自己目的的に、玩具的に運用されていく。
私たちはいつでも、周りから課される制約のなかで、不自由をマゾヒズム的に耐えながら=楽しみながら、生きている。
引用:千葉雅也著『勉強の哲学――来たるべきバカのために』文藝春秋(2017年)P.21
アイロニーとユーモアがごちゃまぜになって、コードが明滅し続ける。contact Gonzoのパフォーマンスは、私たちの慣れ親しんで意識することもない身体の振る舞いを脱コード化し、ぶつかり合いながらも支え確かめ合う、痛みと享楽が同居した両義的な身体のコードを表出させている。

身体と身体が真正面からぶつかり合うパフォーマンスには、緊張感が常に漂っている。しかし、あくまで、相手をノックアウトすることを目的としない。向かってくる相手の身体をたしかに受け止め、もたれ合うような構図からは、むしろ、このままずっと続いてほしいような空気さえ漂っている。さらに言えば、パフォーマンスの終盤には、怪我をしたパフォーマーのひとりに群がって、「手術」シーンが演じられる。ヘッドライトに照らされた患部に、電子レンジで温められた鶏肉があてがわれる。「熱い!熱い!」と叫びながらの荒療治だが、身体をぶつけ合いながらも相手の治癒までを自分たちで担う象徴的なシーンだ。

アイロニーとユーモアは「過剰」になると、ナンセンスな「極限状態」に転化する。
引用:千葉雅也著『勉強の哲学――来たるべきバカのために』文藝春秋(2017年)P.77
*太字は原文ママ
倒れた相手の身体は即物的で、意味がない。残るのはブラックアウトした無意味だけだ。私たちがcontact Gonzoで覗くのは、「ナンセンス(無意味)」の穴なのかもしれない。暗くて深い、その穴を覗きながらも、互いに別の身体接触を差し込み続けることで支え合い、もたれ合いながら、ギリギリで吊り橋を渡っていく。パフォーマンスを眺めながら、私たちはその痛みと享楽を味わっている。

ビンタの残響
音を頼りに感覚の共有を目指してきた今回の新作公演を読み解く上で、contact Gonzoがこれまでずっと探求してきた根源的な身体性に着目して論を進めるのは、あまりに核心を突いていないように思えたかもしれない。
しかし、端的に言えば、パフォーマーたちが感じている痛みや衝撃の感覚を強く共有させられたのは、地鳴りのように鳴り続ける音によってではなかった。むしろその音の荒波に飲まれた祝祭空間がピタリと止まるとき、センサーが検知できなかった、小さなビンタの音がいっそう響いていたように感じられたのだ。
たしかにセンサーの不検知は狙ったものではなく、失敗と見ることもできる。しかし、だからこそ、あの場で起きたビンタのかすかな音のさざなみを、私たちの皮膚や鼓膜のセンサーは微細に感じ取っていた。より正確により多くの情報が検知され、絶え間なく流れる音楽に近づけば近づくほどに、それをしらけさせる空白とかすかな音がむしろ、感覚共有を際立たせる。環境のコードを最大限に前景化させる試みそれ自体が、逆説的に、人間の微細な感覚共有を際立たせる様は、本公演の達成を示しているように思える。ナンセンスの穴を、裏返すかのように深く覗き込みながらも、アイロニーとユーモアをもって綱渡りしていく、マゾヒズムの享楽を観客はたしかに共有していた。

白井瞭 / Ryo Shirai
1993年東京生まれ。早稲田大学文化構想学部卒。2015年、オランダの学際的研究実践機関MediaLAB Amsterdamに留学。2016年に同機関を修了し、リ・パブリックに入社。福井市を舞台とする小さなデザインの教室XSCHOOL、環境省が全国で実施する人材育成プログラムmigakibaの企画運営、高知県・佐川町立図書館さくとの情報環境設計などに携わる。2019年6月、リ・パブリックより、トランスローカルマガジンMOMENTを創刊し、編集長を務める。共著に『アフターソーシャルメディア 多すぎる情報といかに付き合うか』がある。
contact Gonzo パフォーマンス公演
「my binta, your binta // lol ~ roars from the skinland ~」日時:2024年3月1日(金)、2日(土)、3日(日)
会場:ヒルサイドプラザ(東京都渋谷区猿楽町29-10ヒルサイドテラス内)
出演・コンセプト:contact Gonzo(塚原悠也、三ヶ尻敬悟、松見拓也、NAZE)
コンセプトサポート:津田和俊
舞台監督:河内崇
音響設計:西川文章
音響オペレート:溝口紘美(ナンシー)
デバイス設計:稲福孝信
照明デザイン:contact Gonzo
テクニカルサポート:伊藤隆之(CCBT)
ビジュアルデザイン・衣装:小池アイ子
ドローイングアーカイブ:NAZE
制作・進行管理:林慶一、岩中可南子、島田芽生(CCBT)
協力:happy freak