ドキュメンタリーとして描かれた他者は作者の想像の賜物であり、フレームの外側もまた見る者の内側に描かれたものでしかないことは、紛れもない事実だろう。本特集の小田香と磯野真穂による対談で語られたのは、どこまでもわかりえない他者に向かう震える身体と、どこまでもフィクションに内包されていくドキュメンタリーの姿だった。それは、対岸の世界を誰かに伝え、そこに真実を見出したいと願う私たちの敗北を意味するのだろうか。
本稿では批評家・福尾匠が、ある集団と外界の間に横たわる言語の境界と、その突破口を「スパム」と「ミーム」の関係から探っていく。

社会的分断というのは、言葉の面から見れば、あらゆる言葉がその集団の内部ではミームとなり、外部からの、あるいは外部の集団への言葉がスパムとなることを意味するだろう。これは標準語と方言のようないわゆる中心−周縁図式とは異なる社会言語学的な軸として考えることができるかもしれない。
というのも、ミームは特定の集団への帰属を指し示すものではあるが、「標準語」ないし「共通語」に見込まれるような正書法的な(orthographical)規範や由緒正しい歴史をもつものではないからだ。それはすでに何らかの外部性に晒されている、というか、外部性をユーモアで馴化するものがミームだと思う。
たとえば「草生える」というネットスラングの由来を考えてみよう【1】。まず(笑)という記号が日本語対応していないオンラインゲームのチャットで (warai) と表記され、それがネット掲示板や動画サイトのコメント欄へと場所を移しつつ短縮され w になり、さらに、www でその強調が表現されるようになった。この見た目が草が生えているようなので、www と書き込むことが「草を生やす」と呼ばれるようになり——重要なステップだ——最終的に笑うことそれ自体を「草生える」あるいはたんに「草」と言うようになった。
最初に目につくのは (warai) という表記の如何ともし難いぎこちなさだ。(笑)というそれ自体古いものではない、しかし少なくとも日本的な(?)語(?)と、欧米のプラットフォーム、QWERTY配列のキーボード、ローマ字入力という多重の異邦性との衝突が、そこにはあまりに明け透けに現れている【2】。w はたんに倹約的であるというだけでなく多少ともその衝突をマイルドにするものとして一般化したのではないだろうか。そしてこれが外国語の文字としてではなく絵として読み替えられ、草として日本語のエコシステムのなかに位置付けられる(しかしそこには親しい人の知らない表情を垣間見るような微かな違和が残存しており、そのことがミームをミームたらしめる。ryが(略)のミスタイプから生まれたように)。
そしてこの草が文字通り繁茂したのがゲイポルノを笑いのネタにしたいわゆる「淫夢ネタ」の動画コメントにおいてであったことは、見過ごすべきでない点だと思う【3】。異性愛規範に対する外部性を笑いによって馴化するためにこうした、それ自体外部性を隠蔽することで生まれたミームが多用されその外へと拡散された——いまとなっては「草生える」という言葉の使用からプロファイルされるのは30代以下の日本語話者で、ちょっとオタクっぽいというくらいの漠とした特徴だろう——ことは現代の情報技術環境と言語、そしてマクロまたはミクロな政治の絡み合いを考える上で非常に示唆的だ。われわれは異質なものに対して歴史的な正当性によってではなく、すでに成功した——ことすら忘却された、いや、忘却することで成功した——馴化によって他者化しながら包摂するのだ。
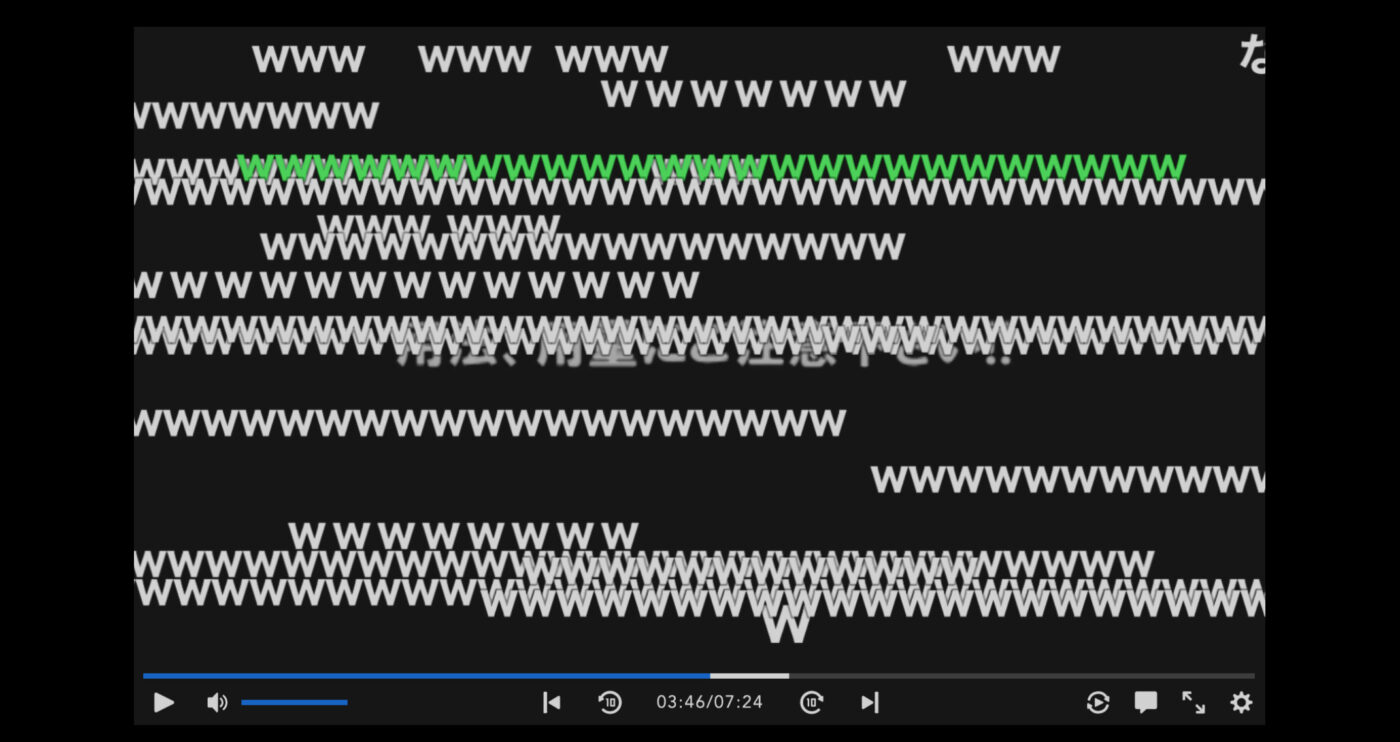
私の知る限り唯一の、スパムを情報技術的−文化的現象として考察した文章は現代美術作家のヒト・シュタイエルによるものだ。彼女は2011年とその翌年に、それぞれ「デジタル・デブリ——スパムとスカム」、「地球のスパム——表象からの撤退」と題された論考を発表した【4】。もちろん、彼女がひとつめの文章でその歴史を概観するように、「スパム」は最初からわれわれの迷惑メールフォルダに振り分けられる、およそ誰にも省みられないような、しかしひたすら真顔で熱心な勧誘の報せを指していたのではない。はじめそれは今でもスーパーマーケットに必ずある、加工され調味された肉の塊を指していた(日本ではとりわけ沖縄でスパムが親しまれているが、これには戦争での牧畜資源の破壊とその後のアメリカによる統治が影響しているようだ【5】)。
シュタイエルによれば、モンティ・パイソンの1970年のコントでウェイトレスがこの肉の缶詰の名前を連呼し客を狼狽させ、インターネット文化の到来とともにスパムは掲示板やチャットを量的に制圧するための機械的に増幅された文字の洪水を意味するようになった【6】。その価値は内容にではなく言葉が占める面積に求められる。この段階から——考えようによってはそれが肉の缶詰しか意味していなかった頃から——スパムはマッシブであることによってスパムとなる。総務省の調査によれば2021年現在でも日本で流通しているメールの40%超がスパムである(2009–2011年は70%前後を推移している)【7】。スパムはデジタル世界のマジョリティ(=多数派)であり、マス(=大衆)なのだ。日の当たる世界ではハッシュタグ・デモに代表されるミーム政治が台頭していることと考え合わせるなら、スパムはまたサイレント・マジョリティであるとも言えるだろう。
いずれも著者ないし発信者の単一性に依らない、その本質からして集合的な言葉であるミームとスパムは、しかし前者はポピュラーであり後者はマッシブである点において、決定的に異なっている。
ポピュラーなミームかマッシブなスパムか【8】。そんなのは偽りの二者択一だ、われわれのコミュニケーションはそんなものでは尽くされないとおっしゃるだろうか? しかしわれわれが血の通った言葉だと思っているものは、結局のところ成功したミームやスパムなのであって、ミームやスパムが失敗した言葉なのではないということを、いったいどうやって反証するのか。つまり二者択一は二重になっている。スパム−ミームの複合体とそれに対置される意味での標準語的なもののいずれを取るか、前者を取る場合スパムとミームのどちらを選ぶのか、と。もしあなたが初手から標準語的なもの——文法的、論理的、歴史−政治的な規範であれ精神的で本源的な共同性であれ——を選ぶとしたら、この文章はあなたのような方にこそ宛てられている。もう少しお付き合いいただきたい。
役者が揃ったところで私としては心おきなくスパムの側にすべてのチップを置いて、あなたにもそうするようこっそり促したいのだが、それにはまだ話が図式的すぎるかもしれない。なぜスパムが擁護されるべきなのかということについて私なりに明確にしてみよう。
シュタイエルがスパムの最初の理論家かつ擁護者として指摘することのひとつは、スパム広告はそのありうべき購買層の「ネガ(negative image)」になっているということだ【9】。スパム広告の画像に登場する、歯列矯正され、脱毛され植毛され、贅肉を吸引され、クリックひとつで金を稼ぐ人間はたしかにフォトショップされた非現実であるだろう。それはわれわれが「そうでないもの」であるところのものだ。彼女がスパムを擁護するのはこのネガティビティにおいてであり、この幽霊的なサイレント・マジョリティが、この星から発せられる膨大な信号を10万光年先なら10万年後に受け取る宇宙人に〈人間〉の何たるかを教えてくれるヒエログリフとなるだろう(彼らには量的勾配以外に人間らしさの輪郭を描く手がかりがないはずだ)。
彼女にとってマッシブなスパムは、文字通りデータ的マイノリティであるわれわれ現実の人間が、われわれを表象し代理する “representation” のシステムから撤退するためのデコイなのであり、つまり見たり見られたりの欲望のゲームからわれわれを解放してくれるイコンなのだ。彼女はスパムを擬人化し次のように語らせる。
「画面から離れなさい」彼ら——スパムのことだ。引用者註——はそうささやく。「われわれがあなたの代わりになろう。その隙に彼ら——宇宙人のことであり、表象のシステムのことだろう。これも引用者註——にわれわれをタグづけさせてスキャンさせてしまおう。あなたは自分のなすべきことをしていればいい」。それが何であれ、彼らは決してわれわれを差し出したりはしないだろう。だからこそ彼らはわれわれの愛と賞賛に値するのだ。【10】

「自分のなすべきこと」というのは、人の目ばかり気にせずスマートフォンを捨てて本を読んだり野に出たり堅実な仕事をしたりせよ、ということだろうか。たしかにそれはスパム自体のイメージや彼らが表立って誘う行為の対極にあるだろうが、そんな誰でも言える良心的なことのためにスパムを擁護するのかと、手段の奇怪さと目的のあっけなさのギャップに戸惑ってしまう。あるいは、それはわれわれがスパムを「差し出す」ことではないか、はたしてそれでよいのか、とも。私が提案する方向修正はふたつだ。
1)彼女はスパム画像をデジタル世界のイコンとして、非現実的な理想を描くものと位置付けているが、少なくとも現代日本のネット環境で目にするスパム広告には、理想的なイメージで惹きつけるものと同じくらい、目を背けたくなる現実を突きつけるものがあるのではないだろうか。それはわれわれの歯がどれくらい汚れていて、鼻の毛穴からどれくらい汚い角栓が飛び出し、腸に詰まった便秘を排出するだけでたちどころに何kg痩せて、体毛が濃くて肥満で貧乏だとどれくらいモテないかということを説いている。シュタイエルの議論ではこうしたアブジェクション的なリアルを掬い取ることができない。それはその非現実性によってわれわれを匿うどころか、「これがお前だ」と詰め寄ってくる。そしてそれは理想的なスパムが実際には誰でもないのと反対に、誰にとってもある程度正しいのだ。
2)シュタイエルは一貫してスパムをイメージの問題として扱うが、私はそれを言語の問題として考えることを提案したい。奇しくも彼女はスパムをわれわれの目から遠ざける自動化された迷惑メールフォルダを「移民に対する防壁、バリア、フェンス」【11】と形容しているが、スパムの言葉はたしかに過度に逐語訳的であったり、あるいは「考えたやつ天才かよ… 神アプリ20選」のような構文もなにもないブロークンな日本語であったりする。言ってしまえばスパムの言葉は「カタコト」なのであり、われわれがスパムをスパムとして認識するとき、われわれの頭のなかには標準語が、正書法が、言語的国境がある。
さて、それでもスパムが「われわれの愛と賞賛に値する」とすれば、それはどのようにしてなのだろうか。シュタイエルはわれわれ自身が、そしてわれわれ自身の言葉がスパムになってしまう可能性を考えていないのではないか。しかし現実として、われわれは決して理想的でも清潔でもない肉塊を引きずって生きており、それがどんなスケールであれ自身の言語共同体の外では必死の呼びかけが「カタコト」呼ばわりされるのだ。
むしろわれわれは積極的に、つまりポジティブにスパムになるべきではないだろうか。スパムへの生成変化。それはミームがその境界の外側にあるもので拵えた入り組んだ防壁を突き破る唯一の可能性だ。われわれはあなたの現実でもある現実を携えて、マッシブな文字で、教科書の例文から取ってきたような見よう見まねの「標準語」で、あなたの半笑いをものともせずに真顔でドアに足を差し込み続ける。10万年後には10万光年先でも。
【1】以下の記述では川添愛「草が生えた瞬間」(『言語学バーリ・トゥード——Round 1 AIは「絶対に押すなよ」を理解できるか』、東京大学出版局、2021年)を参照した。
【2】トーマス・S・マラニーは中国語タイプライターの歴史を辿りつつ、QWERTY的なるものと非アルファベットの言語体系である中国語の間でどのような技術−政治的な葛藤があったかということを非常に鮮やかに描き出している(『チャイニーズ・タイプライター——漢字と技術の近代史』比護遥訳、中央公論新社、2021年)。中国語におけるキーボードへの適応と変換(入力されるキーと出力される文字の分割)という発想の誕生については第6章を参照。
【3】「ニコニコ大百科」の「草不可避」の項目(https://dic.nicovideo.jp/a/草不可避)、およびネットミームの由来を解説する個人サイト「文脈をつなぐ」の「草・草生える・草不可避の意味・元ネタを徹底的に調べてみた」のページ(https://kimu3.net/20170407/7351)を参照。いずれも最終閲覧は2021/09/18。
【4】Hito Steyerl, “Digital Debris: Spam and Scam”, October, no. 138, Fall 2011, MIT Press, https://direct.mit.edu/octo/article-abstract/doi/10.1162/OCTO_a_00067/59125/Digital-Debris-Spam-and-Scam?redirectedFrom=fulltext および “The Spam of the Earth: Withdrawal from Representation”, e-flux Journal, issue 32, February 2012, https://www.e-flux.com/journal/32/68260/the-spam-of-the-earth-withdrawal-from-representation/ (accessed 2021-09-18). 後者については「地球のスパムメール——表象からの撤退」というタイトルで近藤亮介による邦訳が『美術手帖』(2015年6月号、美術出版社)に収録されている。本文での訳出は邦訳を参考にしつつあらためて筆者が行った。
【5】Mire Koikari, “Love! Spam: Food, Military, and Empire in Post-World War II Okinawa”, Devouring Japan: Global Perspectives on Japanese Culinary Identity, edited by Nancy K. Stalker, Oxford University Press, 2018. 本論文では戦後の沖縄におけるスパム(ランチョンミート)の普及に米軍だけでなく、生産元であるホーメル社の世界戦略、アメリカによって設立された琉球大学の家政学教授の言説が関わっていたことがさまざまな資料をもとに論じられている。しかし重要なのは、たんに台所に滑り込み「母の味」となったスパムが統治を脱政治化し、体制を内面化させる権力の象徴であるということだけではない。そこにはいわば、スパムを「ポーク」と呼ぶミームの発生がある。ポークたまごおにぎりやスパムのゴーヤチャンプルーが土着の食文化との折衝のなかで編み出されたように、権力の内面化とそれを逆手に取った創造的なアプロプリエーションの実践は常に両義的な関係にあるだろう。仮にこれが前述の「草生える」に比して「良い」ミームだと言えるのだとしても、私が本稿で問うのははたしてそれだけでよいのかということだ。
【6】Steyerl, “Digital Debris”.
【7】総務省「電気通信事業者10社の全受信メール数と迷惑メール数の割合(2021年3月時点)」https://www.soumu.go.jp/main_content/000693529.pdf(最終閲覧2021/09/18)。
【8】 ドゥルーズ゠ガタリは言語は本質的に集合的なものであるとし、その作動を「言表行為の集合的アレンジメント」として概念化した。私がここで試みるのは、個人的−集合的ないしメジャー−マイナーという対立より深いところにある、ふたつの集合性の対立を取り出すことであり、それは彼らが「母語をどもらせること」と呼ぶ言語の脱中心的な使用の内部に質的な対立を見出すことでもある。彼らの言語論についてはジル・ドゥルーズ゠フェリックス・ガタリ『千のプラトー』(宇野邦一他訳、河出文庫、2010年)上巻に収録された第4プラトーを参照。
【9】 Steyerl, “The Spam of the Earth”.
【10】同前。
【11】同前。
福尾匠 / Takumi Fukuo
1992年生まれ。現代フランス哲学、批評。日本学術振興会特別研究員PD(立教大学)。著書に『眼がスクリーンになるとき:ゼロから読むドゥルーズ『シネマ』』(フィルムアート社)、論文に「ポシブル、パサブル:ある空間とその言葉」(『群像』2020年7月号、講談社)、「ベルクソン『物質と記憶』の哲学的自我:イマージュと〈私〉」(『表象』第14号、表象文化論学会)等がある。メディア「ひるにおきるさる」を批評家・黒嵜想と共同企画。個人サイトtfukuo.comで日記を毎日更新中。
tfukuo.com http://tfukuo.com/
ひるにおきるさる https://note.com/kurosoo/






