「ちょっと電気を落としてみようか」
会場が暗くなる。レクチャーの真っ只中、日暮れの近づく中之島にある会場で、参加者全員が話を止めて窓の外を眺める。それは聴講するというよりは、会場に集まったみんなで今いる場所、そして自分を見つめ直すような時間であった。

2024年11月2日(土)に、無有建築工房の竹原義二さんと、フジワラテッペイアーキテクツラボ(FUJIWALABO)の藤原徹平さんによる対話レクチャー「希望の建築」が、大阪大学中之島センターのホールにて開催された。『住宅建築』の2024年8月号で竹原さんの特集が組まれたこと、そのなかで竹原さんと藤原さんの対談が行われたことを契機に立ち上がった企画だ。主催は竹原さんが長く教鞭をとられている、大阪大学の学生が中心である。
前半に竹原さんと藤原さんそれぞれの講演があり、後半はそれに対して双方の所感が語られ、会場からの質疑も行われた。しかし「対話」と銘打たれたように、単なるスピーカーとオーディエンスの関係にはとどまらない。来場者の話を聞いたり、学生が課題を発表する時間があったりと、会場全体で言葉を交える場が設けられた。

「希望の建築」というタイトルは、竹原さんが大阪大学大学院で11年間実施した授業の表題でもある。ここで題材となったのは、イギリス人の建築批評家チャールズ・ジェンクスと造園家である彼の妻マギー・ジェンクスが設立した「マギーズ・センター」だ。マギー自身が癌を宣告されたときの経験から、死の恐怖のなかでも生きる喜びを見失わず、ひとりの人間として自分らしさを取り戻せる場所が必要だと考え、癌患者とその家族が過ごすためにつくられた場所である。授業ではこのマギーズ・センターを参照しながら、自身や大切な人が宣告を受けたときに過ごす場所として、どんな建築がふさわしいかを考えていった。
大学教育における一般的な設計課題は、計画敷地と条件が出題者によって設定されることが多い。しかしこの授業においては、学生がみな仮定の条件に対してではなく、自分もしくは特定の誰かのために設計を行っていることが印象的だった。病や死に直面したとき、果たしてどんな場所で過ごしたいか、どんな風景が見たいか、どんな空間がふさわしいかと考えること。それは要望に対して回答するというよりも、自身や相手を理解するという設計プロセスを踏んでいるように見えた。どういう人間で、何に価値を感じるかということを顧みて引き受ける。そしてそれを建築を媒介に表明する。そうやってつくられるのは、言わば誰かに希望をもたらすための建築である。
実際に竹原さんは「自身や大切な人が宣告を受けたときに、家族はどういう生き方をするか決断を迫られる。そういった状況や病と向き合うことを助けてくれるのは建築ではないのかと、教えるのではなく学生と一緒に考えてきた」と語っている。答えのない問題に対して、どのように建築を思案するかということを、これまで11年かけて、竹原さんと学生は対話をしながら考え続けてきたのだ。

また竹原さんは、希望の建築を考える上で、これまでの自身の活動について語られた。学生時代の学びや、石井修さんに師事され、その後独立して建築と向き合ってきた歩みなど、特定のプロジェクトについてではなく、建築を通じて場所や歴史に想いを馳せてきた経験である。
今回の会場がある中之島は、竹原さんにとって馴染み深い場所のひとつだ。竹原さんは、1971年に打ち立てられた中之島の開発構想に反対し、取り壊されることとなった大阪府立図書館や大阪市中央公会堂などの既存建築の保存運動を行う「中之島をまもる会」を新建築家技術者集団の仲間と立ち上げた。同会は、中之島の景観維持のみならず、同地を市民活動の場に生かすことを目指し「中之島まつり」を企画。多くの市民を巻き込み、場所の歴史とあり方を考える活動として発展したこのイベントは、現在も受け継がれ2024年で51回目を迎えた。開発構想という社会の大きな流れに対し、本当に中之島にとって良いことは何かを考え、抗った活動である。

一方で藤原さんは、近作である児童養護施設「星美ホーム サローネ」を通じて、希望の建築について考えることを試みている。本プロジェクトの計画地は、カトリック司祭であるドン・ボスコが唱えた理念を掲げる学校・宗教・福祉法人が共存する敷地。老朽化による建て替えを行う際に、法律上の問題で各法人ごとに敷地を分ける必要が生じ、FUJIWALABOが参画したときには、マスタープランのないまま各々の建物単体で計画が進んでしまっていた。
藤原さんはまずこの状況そのものに目を向ける。そして、施設のこれまでの歴史と理念、場所性を顧みるなかで、これまで共存してきた3つの法人を分けるべきではないと考え、用途不可分で敷地を切り離すことができないという立場から法規の整理と行政との協議を行った。また「星美ホーム」は、施設理念の実現に重要な、子どもが遊び、創造活動を行い心を通わせる「サローネ」という場所と運動場を有していたが、これらは建て替えにおける補助金の対象外に。制度からこぼれ落ちた場をどのように再建するかが思案され、最終的に寄付を募るかたちで計画を実施したという。
「建築というのは、建物をつくることだけを考えていてはダメで、それを支えるまわりの都市との関係を戦略的に考えることが大切」と藤原さん。実際にこの施設では、建築と都市における関係の再構築が試みられた。つまり、各法人の理念を引き受け、どうあるべきかを考えた上での制度の設計である。
竹原さんが「中之島をまもる会」で展開した活動のように、藤原さんによるこの施設への実践も、新しい空間を生み出しているわけではない。しかしどちらも、もともとその場所にあったものとその歴史に向き合い、経済性や法律など一見抗うことが難しい現状と対峙している。過去の誰かの想いを読み解き、引き受けようとすることも希望なのだ。

また、建物の設計においても、希望の建築を考えることができる。
このプロジェクトでは、児童養護施設に集まってきた子どもたちが共同生活を送る上で、家族になれるような場所が求められていた。施設理念である「愛されていると感じる」空間とは何か?を設計段階で検討。運営面の効率は重要だが、施設然とした建築にならないこと、子どもたちが安心して過ごせるような中心性をもった空間になることなど、建築の形態を考えるための議論が展開されていったという。
特に印象だったのは、藤原さんの次の言葉だ。「建築という箱を敷地に計画するのではなく、環境に対して素材を編み込んで場所をつくる。環境に対して人間が手を加えるという感覚をもっているかどうかで、建築のありようがかなり違う」
実際にサローネの設計では、合理的構造を考えながらも、建築に働く力の流れや素材同士がどのように組み合わされているかを見えるようにし、建築がただの箱ではなく手仕事の痕跡を感じられるものに変わっていくことを意識している。「Weaving(編み込み)」という単語がプロセスも含めた行為を指すように、藤原さんは建築そのものの形態と、それをどのように組み上げていくかの両方を綿密に計画している。
さらに、編み込むという考え方は、同時に、建築とそれを取り巻く環境の境界が曖昧になることも意味する。藤原さんの事務所が建築だけではなく、ランドスケープを一体として計画しているという態度も非常に理解しやすい。この考え方はマギーズ・センターの理念、そして竹原さんの設計手法とも通ずる。閉じられた建築単体ではなく、建物、ランドスケープ、社会を包括的に扱うことで、環境との適切な関係を模索しているように感じた。

レクチャー終盤では会場を巻き込んだ対話がなされた。竹原さんからはあらためて今我々がいる場所について語られる。自分自身がどういう人間であるか、今いるところがどういう場所か、今の時刻と外がどうなっているかということを立ち止まって、時にはよそ見をしながら考える時間が必要だという。「ちょっと電気を落としてみようか」。そう言って会場の照明が落とされた。
おそらく想定になかったであろうライブ感のある展開だが、それは非常に刹那的で会場全体が「今」のことを顧みる気持ちになったように思う。
15時から開始したレクチャーは終盤を迎え、外はだいぶ暗い。
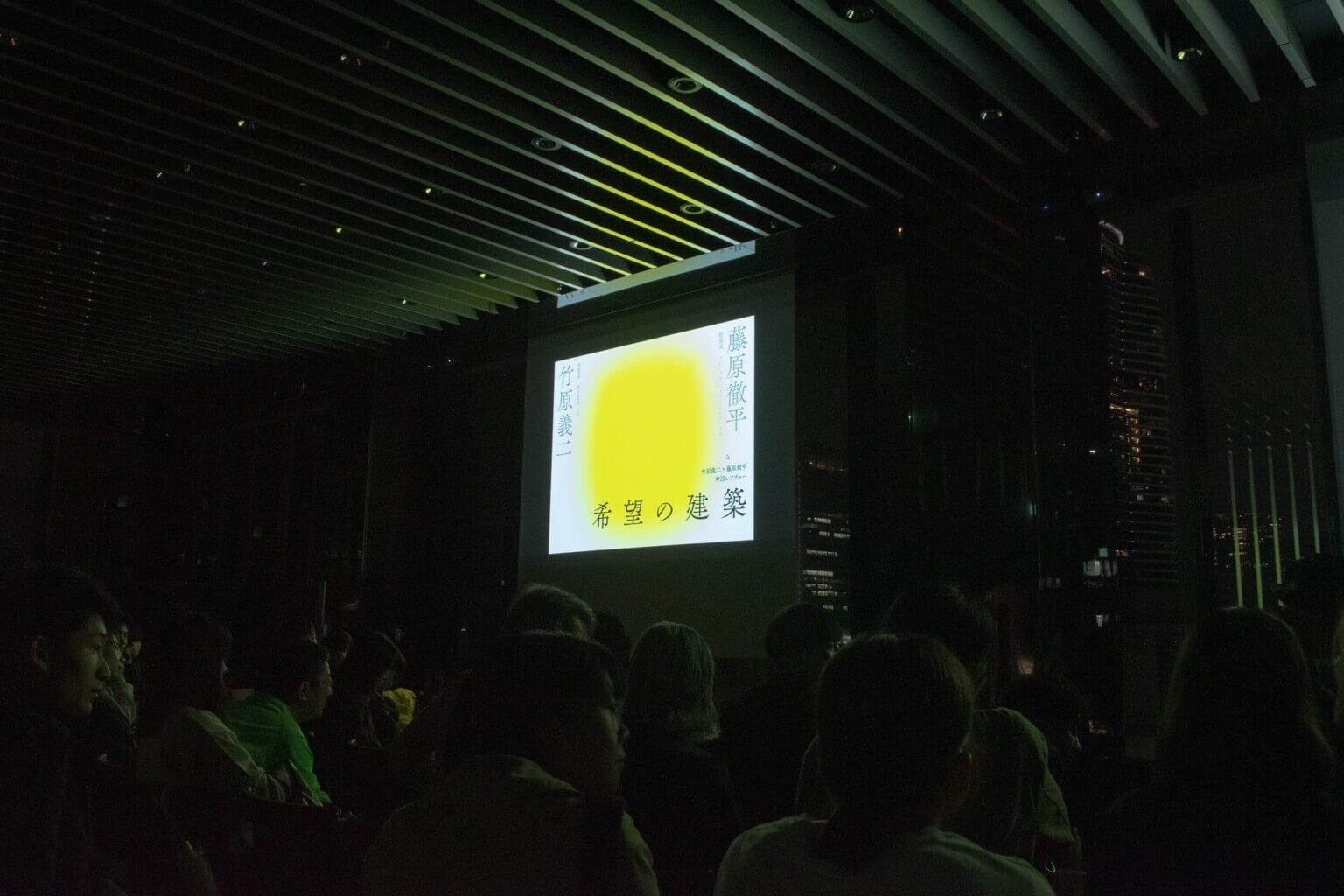
ふたりの話を聞いていると、建築や活動そのものというよりも、ふるまいや態度にこそ希望を見出せるのだと気づく。受け継がれてきた想いや歴史を読み解き、忘れない。そして大切なことは何かと問いかけ、次につないでいく姿勢こそが重要なのだ。
社会を生きるなかで日々に追われ、先しか考えられなくなると、大事なことをすぐに忘れていってしまう。そうならないように、今を顧みる時間が我々にはきっと必要なのだ。そしてそれは、たぶん大それたことではない。仕事中にPCの画面から、ふと窓の外に目をやったり、このレクチャーのように、照明を落として外の光のなかで話をしたり、そんなふうにピントを合わせ直すような些細なことだろう。「一人ひとりがそういう心がけをもって抗うことができれば、希望の建築、希望の社会になるのでは」と藤原さんも言う。
会の最後に主催の学生から挨拶があった。
「竹原先生にはぜひこれからも大阪大学に来て、授業を続けてほしい」
自身が授業で感じたこと、そしてこれからの学生にもそれをつなげたいという意志が見えた。
大阪大学での授業が、学生たちにとって今を顧みる機会となったように、今回のレクチャーも参加者にとって同様の機会になっただろう。たまにこの日を思い出して、大事なことを忘れないように抗うのだ。
日時:2024年11月2日(土)15:00〜18:00 (開場14:30)
会場:大阪大学中之島センター 佐治敬三メモリアルホール
料金:参加無料
主催:大阪大学建築レクチャー学生実行委員会
共催:大阪大学大学院工学研究科 地球総合工学専攻 建築工学部門






