日曜の朝であった。時刻は朝7時をまわった頃。まちを行き交う人の姿はほとんどなく、あたりはまだひっそりと静まりかえっている。展覧会を観に行く時間としては、おそろしく早い。東京を拠点に活動する飯島暉子の展覧会を観るために、大阪の寺田町駅近くの、若い現代美術アーティストらが運営するスペース・NESTに向かっていた。雑居ビルの急な階段を上り、扉を開けると、そこには奥に向かって鋭角に狭くなる三角形の空間が広がっていた。
展覧会を観に来たのに、観るべき作品が何もない。この展覧会は、この奇妙な印象からはじまる。三角形の一辺は全面が摺りガラスとなっていて、曇り空の鈍い光を室内に取り込んでいる。ガラス窓の1枚が30cmほど開いており、そこから外を行き交うクルマやバイクの音が朝の空気とともに室内に入ってくる。室内はガランとしていて、壁にも、床にも作品らしきものは見当たらない。

奥の方で音がして、おもむろに「あ、おはようございます」と、声をかけられた。アーティストの飯島だった。彼女は、展覧会の会期中、近所のホテルに滞在しながらこの場所に通っている。展覧会の案内には、展覧会の時間として「日の出から日没まで」と書かれていて、毎日の鍵の開け閉めを作家本人が行っているらしい。会期中は無休となっているから、展覧会がオープンしている間、彼女はこの展覧会とともに自分の時間を過ごすことになる。ちなみにその日の大阪の日の出の時刻は6時26分だった。
とりあえず三角形をした空間の真ん中に立ってみる。白く塗られた壁と天井に届く日の光、時折けたたましく響くバイクのエンジン音、ひんやりとした朝の空気、まだ覚めやらぬ朝のまちの気配。そうした外部からの「作用」に反応し、それをありのままの状態で受け入れている自分がそこにいた。思考を介してではなく、まさに感応によってその環境と一体になったような感覚である。その瞬間、その体験が何事にも代えがたいとても貴重なものとして感じられた。
会場に用意されたハンドアウトには、作品リストが掲載されていて、展覧会を構成する作品が実際に存在していることがわかる。たとえば《立ち枯れ》という作品。少し空いた窓のそばに、外を眺めるような恰好でわずか2cmほどの消しゴムでできた彫刻が置いてある。表面にはいくつもの細い溝が彫刻刀のようなもので彫られていて、キュビズムの彫刻のような風合いがある。《オーダーメイド》と名づけられた作品は、ドアストッパーだ。展示室の隣の倉庫に通じるドアが開放されていて、そのドアの下に小さな木片をいくつか重ねて押し込んであった。極めつけは、《波》という作品で、素材を見ると「埃」となっている。ハンドアウトのマップには、展示室の床面がその所在場所として示されていて、そこにはいつのものか判別しがたい靴底による汚れがいたるところに見て取れた。



これらの「作品」はいずれも、目立たないように配置されている。いや、意識的にわからないように仕組まれていると言うべきか。つまり、これは「語らない」ことを意図した展覧会なのだ。そもそも、床面の埃を素材にした作品の存在を、作品リストなしに認識することはまず不可能である。実際、過去の展覧会では、作品を識別できぬまま帰ってしまった人から後日、どれが作品であったのか問い合わせが来たこともあったらしい。それは果たして「展覧会」として成立しているのか? ここで問われるのは、飯島が手がける、あえて表現を避けるような芸術行為の意味である。
ここでことさら述べるまでもなく、芸術とは、表現を介して行われる。作家が、他者の内部において何かしらの芸術的な経験を喚起させることを意図して表現を生み出し、それが伝わって芸術は成立する。美術であれば、絵画など目で見て知覚できる表現となる。では飯島の場合はどうであろうか? 彼女が行う表現行為とは、作品に限定されるものではなく、自身を起点に作用を及ぼす「すべて」がそれに当たる。展覧会は、そうした大きな芸術活動の一部に過ぎず、おそらくそれぞれの行為の間には境目がなく、すべてが流動的につながっているのだ。
飯島が大阪に留まるに至った最も大きな理由は、両墓制についてのリサーチであった。両墓制とは、死者の肉体を土に埋めて葬る「埋葬墓」と、故人を偲んで墓参りをする「詣り墓」のふたつの墓を別々に設ける風習である。厳かなる人の死に際して、その肉体と魂を分離し、「真正」と「仮」という見立てを行う。そうした両墓制の流動的なありようが、常に物事の固定化を回避しようとする飯島の意識をとらえたことは想像に難くない。飯島が、作品をあえて目立たなく配置する理由のひとつに、指示的で固定的な見せ方を避ける意味合いがあるのは間違いない。それは鑑賞者が作品を発見できずに帰ってしまう状況も含めて、芸術に触れることへの「自由」を徹底的に担保することでもある。
会場で何に意識を向け、何を発見し、そして何を感じるかは、すべて観る者の自由に委ねられる。しかし、飯島はそこに足を運んだ人を決して突き放したりはしない。彼女は会期中、常にそこにいて、鑑賞者から質問があれば、その背景について丁寧に語ってくれる。展覧会に反応して意識が高まり、知りたい衝動をもつことへの自由を保障しているのだ。そしてその自由は、作家の態度にも及ぶ。作品らしい作品をつくらないという自由。そしてこの展覧会のタイトル「藪」が、飯島が両墓制のリサーチで足を踏み入れた蚊が飛び交う深い藪のことを指しているにもかかわらず、その藪の存在が、展覧会ではいっさい触れられていないということ。それも自由な振る舞いの表れだろう。
しかしここで意識すべきは、その自由は、決して気まぐれで生半可なものではないということだ。彼女の芸術が厳しく存在しているからこそ、その自由は成立する。彼女が、展覧会の時間を通常ではありえない「日の出から日没まで」と定めたり、美術の展覧会に作品らしきものを展示しない態度であったり、そこには自身の活動への徹底的なコミットメントがある。自らの時間を捧げ、批判を受けることへの覚悟のもとで、彼女の芸術は形を現わし、そこではじめて自由の存在が許される。

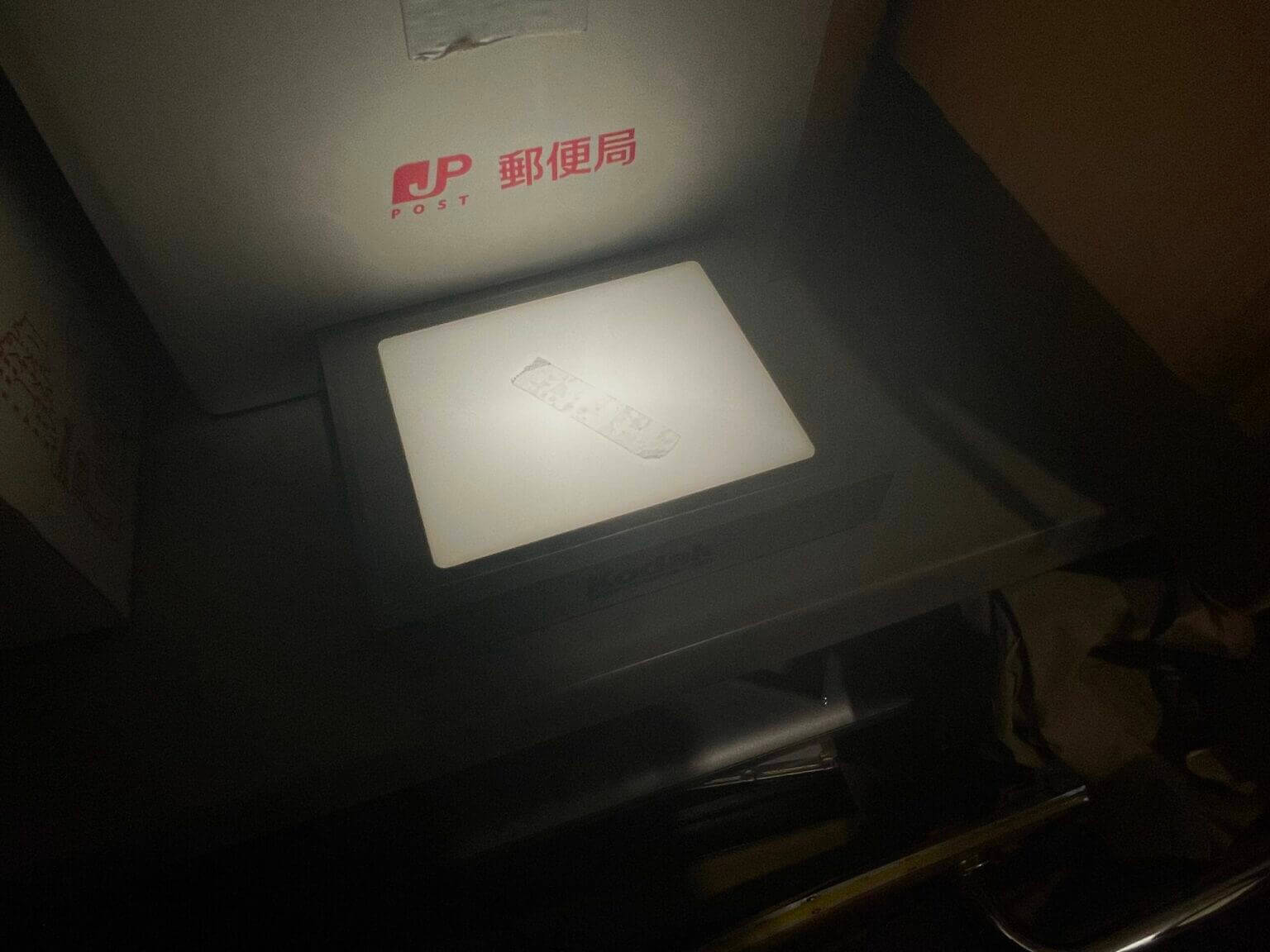
では、飯島の芸術は、私たちにどのような「芸術的」な体験をもたらすのか? それは、展覧会を通して、それまで知っていたはずのものが、新たな価値を帯びて観る者の内面に鮮烈に立ち上がってくること、とあえてしてみたい。現代美術について、苔むすほど聞き飽きた言い回しに聞こえるだろう。しかし、彼女の場合、どこまで本人が意識的であるかは定かではないが、作品というモノを介してではなく、自身が社会彫刻のようなパフォーマティブな存在となることで、表現をしないことの「虚無」を、豊穣な芸術体験を生み出す「表現」へと転化させているのだ。NESTの何もない展示空間は、両墓制のリサーチに費やした膨大な時間と、展覧会を逆相的にあぶり出す揺るぎない信念、日の出から日没までという昔の農民たちが生きた時間を追憶するような実存性によって裏づけされていた。その空間に終始、寄り添い続けた飯島の存在によって、そうした様相が鑑賞者の意識のなかへと染み出していく。その場にいる者が、感覚をより研ぎ澄まし、壁の色、外部のノイズ、空気の温度、光の揺らぎに鋭敏に感応し、そこに意味を見出すことになるのはそのためだ。その虚無から豊穣への転換は、驚くほど鮮やかで、そしてとても美しい。
飯島と話していると、彼女がもつ「初々しさ」への憧憬のような感覚に触れることになる。もともと彼女は油絵を描いていた。しかし、絵筆を握りキャンバスに向かってイメージを固着させていくプロセスによって、美しくかけがえのない「初々しさ」が、対象から徐々に失われていくことを感じるようになる。その「初々しさ」の損耗を回避するため、表現の純化を突き詰めた結果、物質がそのまま表現となる「埃」を素材として扱うようになった。微細な存在である埃を、飯島は、痕跡として多弁な存在であると言う。膨大な時間の集積であり、また剥落した皮膚など身体の痕跡でもあるからだ。しかし埃はゴミであり、ノイズ的な存在である。この埃へと意識を向ける目線が、飯島の作品の本質をまた別の視点から浮かび上がらせる。
つまり、すべては「引き算」なのだ。崇高な精神の発露を思い描く欧米の芸術が表現を加え続ける「足し算」であるとすれば、何かを「演じる」ような振る舞いを見せる美術という制度から、物事を外していくこと。イギリスの作家マーティン・クリードは、何もない展示室の照明をオン・オフするだけの作品で栄えあるターナー賞に輝いた。一見、ミニマムな表現であることから、飯島の作品はそれと似ているように思える。しかし、部屋全体の明滅という見まごうことのない強い表現を持つクリードの作品と飯島の作品はどこか違う。飯島の意識の先には、鑑賞する者の内省的な風景の立ち上がりが強く想定されているに違いない。そこにあるのは、触れた世界がほんの一瞬のうちに見せる「初々しさ」であり、消えゆくからこその美しさである。そのことに気づかせてくれる飯島の芸術は、だから素晴らしいのだ。

大島賛都 / Santo Oshima
1964年、栃木県生まれ。英国イーストアングリア大学卒業。東京オペラシティアートギャラリー、サントリーミュージアム[天保山]にて学芸員として現代美術の展覧会を多数企画。現在、サントリーホールディングス株式会社所属。(公財)関西・大阪21世紀協会に出向し「アーツサポート関西」の運営を行う。
会期:2024年3月8日(金)〜17日(日)※会期中無休
会場:NEST
時間:日の出から日の入りまで
(開催日によって開廊時間が異なります)






