おうちの庭を手入れするように、まちの風景を育てることはできないだろうか。水をやったり花がらをつんだり、ときには土を入れ替えたりと、庭を美しく保つためには手間ひまがかかるが、同時にそれは、暮らしのなかの愉しい時間でもある。こうした日々の庭との関わりをガーデニングと呼ぶように、豊かな社会生活のためのまちへの関わりを「ランドスケーピング」と名づけてみたい。
庭と同じように、まちの風景もまた生きている。だから公園や通りの掃除をしたり、草花の手入れをしたりすることで、まちを育てることが必要だ。私たちはまちの機微を感じとり、その時々に手立てを考え、しなやかに働きかけることで、自分たちの手で美しいまちをつくっていくことができる。
まちを育てる方法はそれだけではない。私たちはまちを眺めるとき、空間だけを見ているわけではなく、そこにいる人たちの過ごし方や表れる雰囲気も含めて、まちを感じている。
たとえば、ラグを広げてピクニックをする、木陰にイスを持ち出して楽器を演奏する、それ自体がまちを使いこなす愉しい時間そのものであると同時に、それがまちの風景の一部になる。そして、それを眺める人たちの悦びにもつながる。「今日は少しお洒落をして、まちに出かけよう」そんな一人ひとりの気分が集まって、まちの風景は彩られている。ランドスケーピングとは、まちに働きかけ、まちを愉しみ、多くの人と影響を与え合う暮らし方のこと。そう考えてみれば、建物や道路をつくらずとも、新しい風景をつくることはできる。
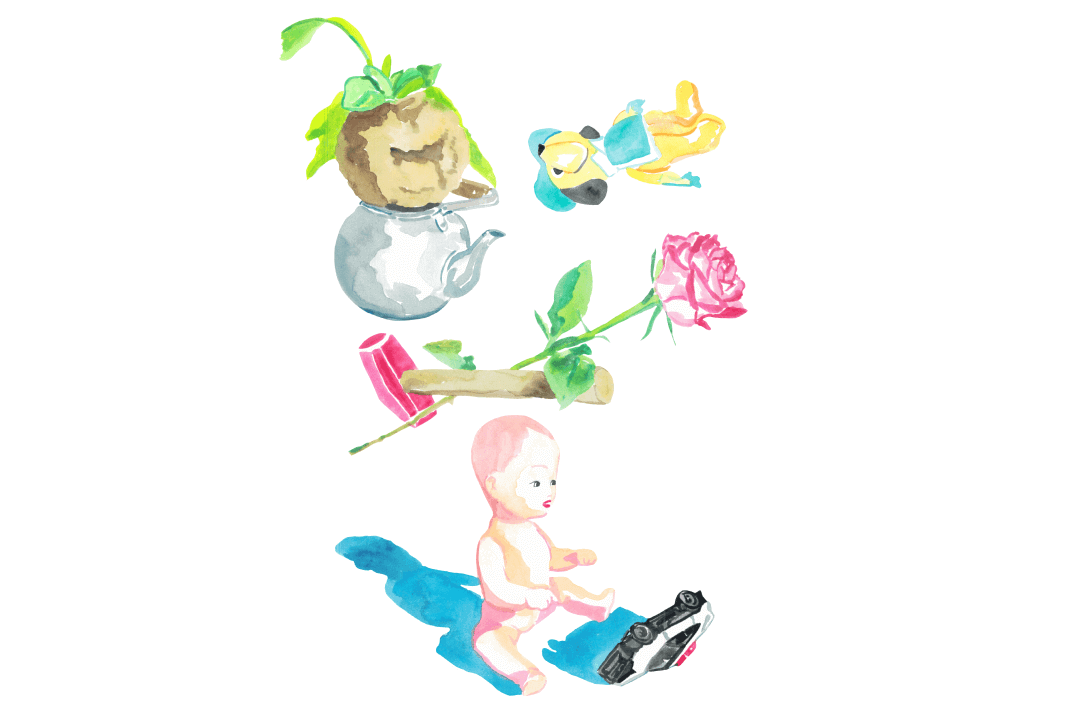
この視点から大阪のまちを見てみると、このまちは人の魅力を風景に色濃く映している。おせっかいであたらしもの好きで、常に関わりを求めている、そんな大阪人の自由な活動を受け入れてくれる包容力がこのまちには備わっている。規律や制限でまちの秩序を保つことよりも、何かおもしろい、ほかにはない、わくわくするものに出会えるまちを大阪人はいつも期待している。さまざまな人の個性がぶつかり合い、響き合う―大阪の風景は、そんな絶え間ないまちと人とのコミュニケーションによって育てられてきた。そこには、まちは「誰かにつくってもらうものではなく、自分たちがつくっていくものだ」という気概が感じられる。そんなまちに対する親密さや自負こそが大阪のランドスケーピングの本質だ。
武田重昭 / Shigeaki Takeda
1975年神戸市生まれ。ランドスケープ・アーキテクチュアの視点から都市と人生を魅力的にする「パブリックライフ」がつくる風景について研究。著書に『小さな空間から都市をプランニングする』(編著、学芸出版社)など。

大阪・関西万博の開催を前に、2025年以降の世界を想像し、自分たちの足元から暮らしを考えるメディア。イギリスの社会人類学者 ティム・インゴルド氏のインタビューや、大阪・関西を拠点に活動する研究者、クリエイターによるコラムを掲載。
監修は、デザイン視点から大阪・関西万博で実装すべき未来社会の姿を検討する試みとして2021年12月に発足した「Expo Outcome Design Committee」が務め、デザイン・編集には大阪・関西を拠点に活動するさまざまなつくり手が名を連ねている。
タブロイド版は全国各地の美術館や書店などで配布されており(配布先はマップ参照)、Web版も公開中。
発行日:2022年3月31日
発行元:公益社団法人2025年日本国際博覧会協会
監修:Expo Outcome Design Committee(原田祐馬・齋藤精一・内田友紀)
企画:原田祐馬
共同企画・編集:多田智美・永江大・羽生千晶(MUESUM)+白井瞭(MOMENT)
デザイン・印刷設計:芝野健太+松見拓也
INTERVIEW編集協力:井上絵梨香(MOMENT)
VOICE編集協力:竹内厚
COLUMNイラストレーション:權田直博
印刷・製本:株式会社ライブアートブックス






